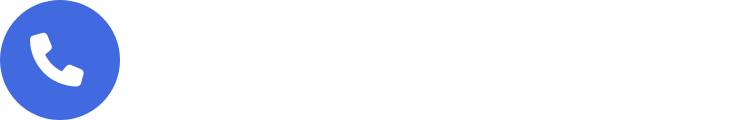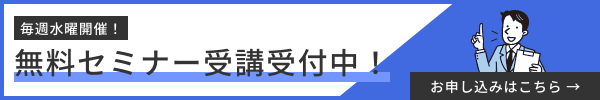【経営・管理ビザ】更新申請で重要な改正基準要件
2025年11月13日
経営・管理ビザ
【経営・管理ビザ】更新申請で重要な改正基準要件
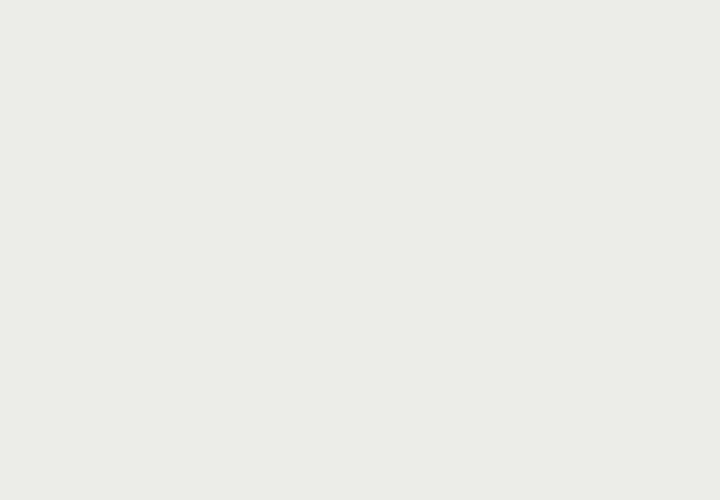
内容
3.更新の経過措置対象は2025年10月15日までに「経営・管理」を申請又は許可された者… 2
5.2025年11月以降の「経営・管理」ビザ更新申請まで早めに準備したい書類一式例… 4
6.更新が不許可になりやすいケース(改正後経営・管理)… 4
2025年10月16日、出入国在留管理庁は在留資格「経営・管理」に関する
- 「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)」と
- 「出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)」
の一部改正を施行しました。これにより、これまで新規取得時に求められていた事業規模・実在性の確認が、変更・更新にもより明確に波及する運用になります。
更新における今回の改正のコアは次の3点です。
- 資本金(出資総額)の下限が3,000万円に引き上げられたこと
- 本邦居住の常勤職員を1名以上雇用することが必須になったこと
- 申請者または常勤職員のいずれかに相当程度の日本語能力を求めること
更新は入管法21条に基づき「在留を引き続き適当と認めるとき」に許可されます。この「適当かどうか」を判断する際に、入管法7条1項2号でいう「法務省令で定める基準」に準拠しているかどうかを改めて確認するというのが入管庁ガイドラインにおける考え方です。
つまり、上陸基準省令が改正されると、その後の在留期間更新でも入国時や変更時と同じ基準が問われます。
3.更新の経過措置対象は2025年10月15日までに「経営・管理」を申請又は許可された者
公表資料では、施行日より前から「経営・管理」で在留している人については最大3年間の緩和的な取り扱いが示されています。すなわち、2025年10月16日から2028年10月16日までの間にする更新については、改正後基準を完全に満たしていなくても、事業の成長見込み・公租公課の履行状況・次回までに充足する計画などを総合して判断するとされています。例えば、2025年から2出す更新は、当面この「猶予期間」になります。
ただし、緩和される猶予期間でも「全く事業実体がない」「雇用も社会保険も未整備」「納税不履行」などの場合は更新が難しくなります。緩和は「猶予」であって「免除」ではないと説明しておくと親切です。
改正後の上陸基準省令では、次の両方を求めています。
- 申請者以外に、本邦に居住する常勤の職員が1名以上従事していること
- 資本金の額または出資の総額が3,000万円以上であること
(従来あった「これらに準ずる規模」緩和は削除)
※更新時に3,000万円に届いていない場合でも、増資実行中/出資契約締結済み等を専門家書面で示して「次回までに充足見込み」を立証する運用が想定されています(緩和期間内)。
申請者または常勤職員のどちらかが、日本語教育の参照枠B2相当(実務的にはJLPT N2など)以上を有することが求められます。日本人又は特別永住者などを常勤に置いている場合はこの日本語要件までクリアしやすいので、更新では「誰でこの要件を満たしているか」を書面で明示しておくと安全と考えられます。
事業計画の具体性・実現性を、中小企業診断士・税理士・公認会計士などの経営専門家が確認した書面を付けることが求められます。これは「書類があるだけ」の会社をふるい落とす狙いがあるので、更新でも「計画どおりの進捗か」「修正計画を専門家がどのように見ているか」を説明するページを添付すると安全と考えられます。
従来どおり、事業所が実在し、該当事業の許認可を取得しているかを資料で示す必要があります。
公租公課としては、法人税・消費税・源泉所得税・社会保険の納付状況を確認し整理してから出すことが重要です。
5.2025年11月以降の「経営・管理」ビザ更新申請まで早めに準備したい書類一式例
- 在留期間更新許可申請書(改正後様式)
- 事業内容・事業実績の説明書(前回申請以降の変化とその理由を記載)出典:法務省
- 常勤職員の在籍証明・雇用契約
- 資本金3,000万円を示す登記事項証明書・株主名簿・増資関連議事録(不足している場合は増資計画と専門家確認書)
- 日本語能力を証する書類(JLPT N2合格証・日本人職員の住民票など)
- 住民税などの納税証明
- 社会保険の加入・納付状況を示す書類
- 業法上の許認可の写し(建設業、旅館業、宅地建物取引業、廃棄物処理業など、在留後取得が認められていたものはこの更新で提出)
- 資本金が500万円のままで、増資などが一切できないほど財務が良くない
この場合、資金調達なども選択肢です。 - 常勤職員がいわゆる就労ビザである「法別表第一の在留資格」の外国人だけで、日本人等の常勤がゼロ(新基準の常勤にカウントされないため)
技術・人文知識・国際業務等も不可能 - 日本語要件を満たす人が社内に一人もいない
- 税や社会保険の未納がある
- バーチャルオフィス・自宅兼用事務所であり事業所確保の程度を証明できない
2025年10月16日(実務上は同年11月申請分以降)からは、「経営・管理」在留期間の更新でも、原則として改正後の事業規模・雇用・日本語・専門家関与の各要件を満たしていることが前提となります。
もっとも、施行日前から在留している方には最長3年間の経過的取扱いがあります。ただし、この場合でも現状の会社の体制と、次回までに整える計画を提出することがありえます。
少しでもご不安があれば谷島行政書士法人グループにお声がけください。
関係法令
出入国管理及び難民認定法
・第7条第1項第2号(上陸の条件として法務大臣が定める基準に適合すること)
・第20条(在留資格の変更)
・第21条(在留期間の更新)
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)
・令和7年10月16日施行改正分 「経営・管理」の項:
1. 事業計画と専門家確認
2. 本邦居住の常勤職員1名以上
3. 資本金又は出資総額3,000万円以上
4. 申請人又は常勤職員の日本語能力
(官報:令和7年10月10日号外第227号)
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)
・在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請に添付すべき書類に関する改正(令和7年10月16日施行)
出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」提出書類一覧ページ(2025/10/16施行版)
出入国在留管理庁公表資料「『経営・管理』の許可基準の改正等について」(更新・永住への影響、3年間の経過措置に言及)
CATEGORY
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。
- 対応サービス
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他