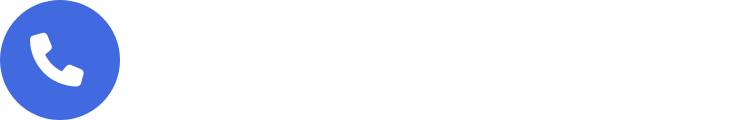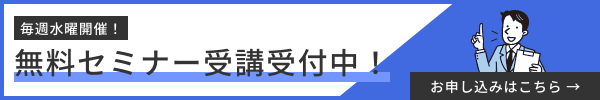外国人雇用に必須なのは入管法(ビザ法制)と労働法のミックス
2025年07月29日
行政法実務コンプライアンスサービス在留資格一般
外国人雇用に必須なのは入管法(ビザ法制)と労働法のミックス

内容
外国人雇用は入管法がメイン。プラス「なぜ労働法の知識も必須」なのか?
日本人に対しても、労働法で合法かつ入管法違反にならないようにする
外国人雇用のトラブルを防ぐ第一歩:停止条件と解除条件を使いこなす
外国人材の雇用が一般化する現代において、企業担当者の皆様が直面するのが、出入国在留管理庁(入管)への手続きと、日本の労働法の遵守という2つの大きなテーマです。これらは一見別々の問題に見えますが、実は密接に連携しており、一方の知識が欠けていると思わぬトラブルに発展する可能性があります。
本記事では、外国人雇用においてなぜ労働法の知識が不可欠なのか、特に注意すべきポイントはどこなのかを、具体的な事例を交えて解説します。
外国人雇用は入管法がメイン。プラス「なぜ労働法の知識も必須」なのか?
「労働法のことは、顧問の社会保険労務士に任せているから大丈夫」とお考えの企業様も多いかもしれません。もちろん、労務管理の専門家である社労士の先生との連携は非常に重要です。
しかし、こと外国人雇用に関しては、まず行政書士がビザ(在留資格)申請の場面で、企業の労働法遵守状況を確認する必要があります。なぜなら、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」といった主要な就労ビザの申請において、適正な労働条件が確保されていることが許可の要件となっているからです。
つまり、入管法令・ビザの前提として、労働法の理解が不可欠なのです。特に、以下の法律は(最初は浅くてよいので、)最低限押さえておく必要があります。
労働基準法
- 労働契約、賃金、労働時間、休日、休暇など、労働条件に関する最低基準を定めた法律です。全100条あまりと比較的コンパクトですが、外国人材を含め、日本で働くすべての人に適用される基本の法律です。入管にも労働基準法の違反に対する処分権限があります。
労働安全衛生法
- 特に建設業や製造業など、現場作業を伴う職場で重要になります。例えば、特定の重機やクレーンの操作には「特別教育」の実施が義務付けられています。また、従業員の安全と健康を守るための「健康診断」の実施もこの法律で定められており、これらはすべて外国人材にも等しく適用されます。入管にも労働安全衛生法違反に対する処分権限があります。
労働契約法
o 労働契約の成立、変更、更新及び解雇などの規定を定めている法律です。違反があれば入管法の許可要件に直結します。刑事罰がないのですが、入管にも労働契約法違反に対する処分権限があります。したがって、労働基準法や入管法違反につながる場合、行政処分や刑事罰にも発展します。
最低賃金法
o 所定労働時間数などを踏まえて残業との関連を整理したうえで、外国人雇用の労働契約書を作る必要があります。外国人雇用に関しては、入管にも最低賃金法などの違反に対する処分権限があります。
日本人に対しても、労働法で合法かつ入管法違反にならないようにする
例えば、普通解雇については、外国人雇用で上乗せが入管法の特定技能基準省令で存在します。具体的には、非自発的離職は適法であり、かつ解雇無効につながらない方法として利用されています。
しかし外国人雇用がある企業であれば、日本人に対しての離職であっても、一年間「特定技能の受入停止処分」につながる規定があります(特定技能基準省令第2条二)。
| 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令 (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)第二条 法第二条の五第三項の法務省令で定める基準のうち適合特定技能雇用契約の適正な履行の確保に係るものは、次のとおりとする。 略 二 特定技能雇用契約の締結の日前一年以内又はその締結の日以後に、当該特定技能雇用契約において外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者(次に掲げる者を除く。)を離職させていないこと。 (イロハは略) ニ 自発的に離職した者 |
非自発的離職は、労働法令で認められている「肩たたき」類型も該当するため、労働法より広いと思ってください。誤解があると入管から処分をうけることになります。
最大のリスク!在留資格の失効が「解雇」に直結しない現実
外国人雇用における最大のリスクの一つが、このセクションで解説する「雇用契約と在留資格の関係」です。
よくある誤解として、「在留資格が更新できなかった(不許可になった)」「在留資格を取り消された」といった場合に、企業が自動的にその外国人を解雇できる、というものがあります。
しかし、これは大きな間違いです。 在留資格の許可・不許可は、あくまで国がその外国人の日本での活動を認めるかどうかの「行政上の判断」に過ぎません。それ自体が、企業と従業員との間で結ばれた「雇用契約」の有効性を直接左右するものではないのです。
もし、在留資格を失ったことだけを理由に一方的に解雇通知を出した場合、それは「普通解雇」として扱われます。ご存知の通り、日本の労働法上、企業側からの解雇は非常に厳しく制限されており、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は「不当解雇」として無効になる可能性があります。
万が一、不当解雇を巡って訴訟などに発展した場合、企業は深刻な金銭的・時間的損失を被るリスクを負うことになります。
外国人雇用のトラブルを防ぐ第一歩:停止条件と解除条件を使いこなす
では、どうすればこのリスクを回避できるのでしょうか。 その答えの一つは、雇用契約書に特別な条項を設けることです。具体的には、「停止条件」と「解除条件」という2つの考え方を活用します。
弊社顧問では、個別にカスタマイズします。また労働契約書と雇用予定書を使い分けます。
その上で、停止条件と解除条件を活用します。会社のリスクヘッジとしても重要なので、個別に提案する必要がありますが、イメージできるよう以下の例を示します。
- 停止条件付契約の例
- これは、「在留資格の取得」を条件として、雇用契約の効力が発生する、という契約形態です。
- 条文例:
- 第〇条(効力発生)
- 本契約は、〇〇(従業員名)が就労可能な在留資格を適法に取得し、その在留カードを甲(会社名)に提示したときにその効力を生じるものとする。
- これにより、万が一ビザが不許可になった場合でも、そもそも雇用契約の効力が発生していないため、「解雇」という問題自体を回避できます。
- 解除条件付契約の例
- これは、在留資格の喪失をもって、雇用契約が自動的に終了する、という取り決めです。
- 条文例:
- 第〇条(契約の終了)
- 〇〇(従業員名)が、その保有する在留資格の有効期間を満了し、または在留資格を取り消されるなど、日本国において適法に就労する資格を喪失した場合には、本契約は当然に終了するものとする。
- この条項があれば、在留資格の更新ができなかった場合などに、解雇ではなく、契約条件に基づく「合意による契約終了」として、スムーズに雇用関係を解消できます。
これらの条項を雇用契約書に適切に盛り込むことで、在留資格という行政面の法令遵守と許認可維持、及び手続を踏まえ、それらを雇用契約と連動させ、将来の予期せぬトラブルから会社を守ることが可能になります。
行政書士顧問サービスによる外国人雇用の労働法
当法人では、外国人雇用を専門とする行政書士が、貴社の状況に合わせた最適なサポートを提供する「顧問サービス」をご用意しております。
一般企業のみならず、弁護士や社会保険労務士からもご依頼可能です。
谷島行政書士法人グループでは、代表が労働法を行政書士受験科目として高得点をとっております(今の行政書士試験制度では労働法の出題は少ないです)。
また外国人雇用部門のスタッフも独自の育成システムにより労働法を学び、また外部研修も受け、実践でアウトプットしております。
単なるビザ申請の代行に留まらず、
- リスク回避のための雇用契約書・労働条件通知書の作成およびレビュー
- 入管法・労働法の法改正に対応した社内規定の整備
- 日々の労務管理に関するご相談への対応
- 在留資格の更新・変更手続きの計画的な管理
など、外国人雇用に関するあらゆるフェーズをワンストップで支援いたします。 専門家が継続的に関与することで、担当者様の負担を大幅に軽減し、企業が安心して事業に集中できる環境を構築します。
まずはお気軽に、当法人の初回無料相談をご利用ください。貴社の現状をヒアリングさせていただき、最適なご提案を差し上げます。
まとめ:専門家と共に、盤石な外国人雇用体制を
ここまで解説してきたように、外国人雇用を成功させるためには、入管法と労働法の両方を見据えた、戦略的な労務管理が不可欠です。特に、すべての土台となる雇用契約書の整備は、まさに企業の「防衛線」と言えるでしょう。
しかし、多くの企業様では、既存の日本人の雛形をそのまま流用していたり、ネット上の不確かな情報で作成していたりと、リスクのある契約書を運用してしまっているケースが散見されます。問題が発生してから専門家に相談しても、打てる手は限られてしまいます。
したがって、事前に依頼し、予防法務観点で法令遵守体制を万全にする必要があります。
CATEGORY
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。
- 対応サービス
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他