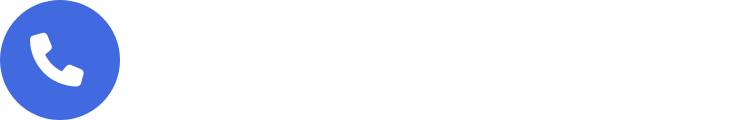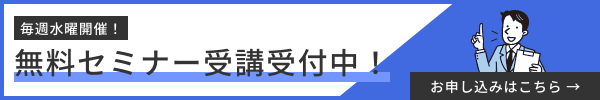「技術・人文知識・国際業務」ビザの派遣企業にメス?入管庁による不法就労の実態把握で変わること
2025年08月28日
コンプライアンス技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」ビザの派遣企業にメス?入管庁による不法就労の実態把握で変わること

内容
2025年、出入国在留管理庁(以下、入管庁)が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で就労する外国人の派遣労働について、実態把握を強化する方針を示したというニュースが報じられました。
▶「入管庁、外国人の派遣労働把握へ 専門職資格で単純作業、是正必要」
ニュース記事では、「本来禁止された単純作業を派遣先で担うケースなどを確認、是正が必要と判断」をされております。
これは、専門的人材である「技術・人文知識・国際業務」の外国人を違法に派遣することで不法就労助長罪として逮捕される事例も昔からあった問題です。
例えば、新宿中村屋さんで派遣されたネパール人を国際業務として、肉まん工場の作業員で働かせ、工場の管理課係長が逮捕されたという朝日新聞の記事もあります。
▶「カレーの中村屋、「人手不足」でネパール人を不法就労させた疑い」
この動きは、長年にわたり問題視されてきた「不法就労派遣」とも言える不適切な就労実態に、いよいよメスが入ることを意味します。専門職として期待される外国人人材を適正に雇用し、受け入れるため、すべての企業様に関わる重要なテーマです。
本記事では、この問題の背景と、今後の企業実務に与える影響について、専門家の視点から詳しく解説します。
なぜ今、「技人国」の派遣が問題に?
「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国」)は、大学等で学んだ専門知識を活かす業務(例:ITエンジニア、翻訳、マーケティング、経理など)に従事するための在留資格です。
この「技人国」には、他の就労資格(特定技能や技能実習など)と比べて、派遣という働き方が比較的容易であるという特徴があります。具体的には、派遣元の企業が「技人国」の在留資格を申請・取得すれば、派遣先企業の個別な許可なく、労働者を派遣することが可能です。これは、「技術・人文知識・国際業務」が転職の自由度も比較的高いとされていることも要因です。
この制度の柔軟性を悪用し、一部の悪質な派遣会社が長年、以下のような手口で不適切な就労をさせてきた実態があります。
- 手口の例:
- ① 派遣会社が「翻訳・通訳業務」などの専門職として外国人を雇用し、「技人国」の在留資格を取得させる。
- ② しかし、実際の派遣先は申請内容と全く関係のない食品工場や物流倉庫など。
- ③ 派遣先では、専門知識を必要としない単純労働に従事させる。
このような行為は、在留資格で許可された活動範囲を逸脱する「資格外活動」にあたり、出入国管理及び難民認定法に違反する違法な状態です。この問題は10年以上も前から指摘されていましたが、入管庁が本格的な実態把握に乗り出すことで、状況が大きく変わろうとしています。
入管庁の「実態把握」で何が変わるのか?
今回の入管庁の方針強化は、単なる調査にとどまらず、実効性のある施策となる場合、今後の在留資格申請の審査に大きな影響を与えると考えられます。
これはいわゆる「上陸基準省令」等を改正するだけで派遣に対する上乗せ屋横出しの要件設定も可能です(「委任命令」と呼ばれる省令改正だからです)。
さらに、入管法施行規則の改正もすることで申請書等の項目も変更可能です(「執行命令」と呼ばれる省令改正だからです)。
派生する論点①:申請・更新、さらには届出の厳格化
今後、特に派遣形態で外国人を雇用する場合、在留資格の新規申請や更新申請において、以下のような点が厳しく審査される可能性があります。
- 具体的な業務内容の明確化: 派遣先でどのような業務に、どの程度の割合で従事するのか、より詳細な説明が求められるようになります。曖昧な「翻訳業務」といった記載だけでは不十分と判断される可能性があります。
- 提出資料の追加: 具体的な業務内容を示す資料の提出が求められるようになることが予想されます。
これは、派遣をする際の「所属機関等に関する届出」時に、提出を求められるようになる可能性もあります。
- 更新時の実績確認: 更新申請の際には、過去の活動内容が当初の申請通りであったか、給与の支払い状況などと合わせて厳格にチェックされるでしょう。申請内容と異なる単純労働に従事させていた場合、在留資格の更新が不許可となるリスクが非常に高まります。
派生する論点②:派遣先企業にも問われる「受け入れ責任」
これまで、派遣労働者の在留資格に関する手続きは、主に派遣元企業の責任とされてきました。しかし、審査が厳格化されると、派遣先企業も無関係ではいられません。
- 不法就労助長罪のリスク: 派遣先企業が、受け入れている外国人が在留資格の範囲外の活動(単純労働など)を行っていると知りながら働かせた場合、不法就労助長罪に問われる可能性があります。「派遣会社から紹介された人材だから大丈夫だと思った」という言い分は通用しません(過失とされるには限定的で厳しいため、罰則適用がないと評価されることはあまりありません)。
- 確認義務の発生: 今後は、派遣労働者を受け入れる際に、その外国人が従事する業務内容が、在留資格の範囲内であるかを自社でも確認することが、コンプライアンス上、極めて重要になります。
企業が今すぐ取るべき対策
この変化に対応するため、派遣元・派遣先の両企業は、以下の対策を講じることを強くお勧めします。
- 契約内容の再確認
- 労働者派遣契約書に記載されている業務内容が、実際の業務と一致しているか、また「技人国」の活動範囲内であるかを改めて確認してください。
- 業務実態の把握
- 派遣労働者が実際に行っている仕事内容を正確に把握し、専門性を要しない単純労働になっていないかを確認してください。
- 専門家への相談
- 自社の受け入れ体制や契約内容に少しでも不安がある場合は、私たち行政書士のような専門家にご相談ください。最新の入管庁の動向を踏まえ、適法な体制構築をサポートします。
今回の入管庁の動きは、外国人材の適正な保護と、日本の在留資格制度の信頼性を確保するための重要な一歩です。これを機に、ぜひ一度、社内の外国人材の受け入れ状況をご確認ください。
「不法就労の派遣」に、谷島行政書士法人グループの解決策
この派遣外国人雇用の不法就労の問題は、人手不足の企業に対する需要と、外国人雇用を理解しきれていないことが原因であるとされるケースが多いです。
そこの根本的な解決策は、企業ごとの状況整理をしたうえで、入管法に則ってアプローチすることが重要です。
例えば、研修プログラム作成の「技術・人文知識・国際業務」で許容される現場系就労もあります。
また「特定技能」で雇用することのコンプライアンスなどのコストが高い企業には、コストダウンを提案することも可能です。
個別ケースに応じたクリエイティブなアプローチは、谷島行政書士法人グループに強みがあります。
ご不明な点は、顧問行政書士や谷島行政書士法人グループにご相談ください。
CATEGORY
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。
- 対応サービス
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他