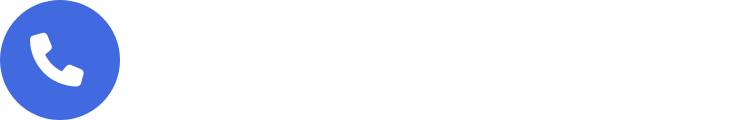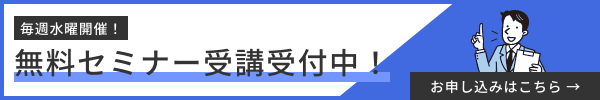永住権取得の徹底解説シリーズその1(令和6年改正入管法対応)
2025年05月16日
永住
永住権取得の徹底解説シリーズその1(令和6年改正入管法対応)

外国人従業員の皆様が日本での生活基盤を安定させ、安心して長期的に活躍するためには、いわゆる「永住権」の取得が重要な選択肢となります。
そもそも永住権とは、入管法に基づく「永住許可」申請が許可されることで在留資格「永住者」になる状態を指します。
在留活動に制限がなくなり、在留期限・期間もなくなります。日本人に近いかたちで仕事が自由になり、住宅ローンも含め生活やキャリアの選択肢が広がるなど、様々なメリットがあります。
本解説ページは、Stepごとに把握しておく知識をセクション別に学べる章立てにしております。それにより、企業の人事担当や外国人従業員が永住許可申請をサポートされる際に必要となる知識を網羅的に提供することを目的としています。
永住申請の基本から、見落としがちな注意点、2024年成立改正法(公布から3年以内施行)の要件や運用まで、分かりやすく解説します。
目次
第2章:永住許可(Step 2)の対象となる主な在留年数及びケース一覧
第3章:永住申請(Step 3)における、独立生計や、収入に係る公的義務の国益要件(収入、納税、社会保険)
第4章:永住申請 (Step 4):素行善良要件と、それを兼ねる国益要件の詳細
第5章:永住申請 (Step 5):手続の流れと不許可リスクへの注意点
第6章:永住申請(Step 6):全体のポイントまとめ、許可率統計データ、行政書士代行の要否
永住許可の基本要件 (Step 1)
まず、永住権とは何か、そして外国人従業員や企業にとって、なぜ永住権取得が重要なのかをご説明します。
日本の在留資格には様々な種類がありますが、大別すると「活動内容に制限があるもの(例:技術・人文知識・国際業務、技能実習など)」と「活動内容に制限がないもの(例:永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)」に分けられます。
永住権(「永住者」の在留資格)は、このうち活動内容に制限がない在留資格の一つです。一度取得すれば、原則として在留期間の更新手続きが不要となり、日本での生活や就労において大幅な自由が得られます。これは、外国人従業員の方にとって大きな安心感となり、企業にとっても長期的な雇用計画を立てやすくなるなどのメリットをもたらします。
永住権取得のメリット
- 在留期間の制限がなくなる: 原則として在留期間の更新が不要となり、在留期限を気にすることなく日本に滞在できます。
- 活動内容の制限がなくなる: 就労資格の種類に縛られず、どのような仕事に就くことも、事業を立ち上げることも自由になります。
- 社会的な信用が高まる: 住宅ローンを組みやすくなる、事業資金の融資を受けやすくなるなど、日本での社会生活において様々な面で有利になります。
- 家族の呼び寄せが容易になる: 永住者の配偶者や子供は、比較的容易に在留資格を取得できるようになります。
- 再入国許可手続きが簡略化される: 再入国許可の有効期間が最長5年(特別永住者は6年)となり、海外渡航がしやすくなります。
これらのメリットは、外国人従業員のモチベーション向上や日本への定着促進に繋がり、結果として企業の競争力強化にも貢献します。
永住権を取得するためには、主に以下の3つの基本要件を満たす必要があります。(入管法令及び出入国在留管理庁が公表しているガイドラインに基づきます。)
法律上の永住許可要件は以下の通りです。
- 素行が善良であること(素行善良要件)
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)
- その者の永住が日本の国益に合すること(国益適合要件)
これらの要件は包括的であり、個別の状況に応じて総合的に判断されます。なお、改正による追加箇所は以下の「国益要件」における下線部です。
| 出入国管理及び難民認定法
(永住許可)第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。 2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。 一 素行が善良であること。 二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。 |
これによって入管法の届出を含む義務履行まで、すべて要件として法令明示されました。
別章にてそれぞれの要件について詳しく解説します。
CATEGORY
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。
- 対応サービス
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他