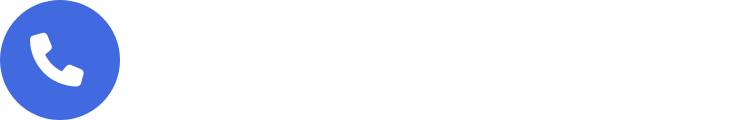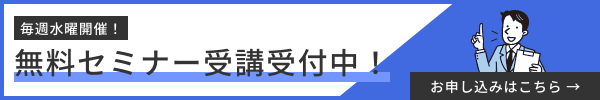特定技能の自動車運送業に必要な免許、許認可、研修、試験等:業務区分ごとに解説
2025年03月15日
特定活動特定技能許認可
特定技能の自動車運送業に必要な免許、許認可、研修、試験等:業務区分ごとに解説

内容
対象業務
特定技能1号の特徴
特定技能所属機関に課される主な条件
(1)貨物自動車運送業
(2)旅客自動車運送業
(3)貨物利用運送業
(4)安全・労働環境の認証
(1)技能試験
(2)日本語試験
(3)運転免許
(1)一般貨物自動車運送事業許可:トラック運送
(2)一般乗用旅客自動車運送事業許可:福祉輸送
(3)第一種貨物利用運送業登録:トラック運送
(4)第二種貨物利用運送業許可:航空、内航、外航の外国人
(5)倉庫業登録その他
企業側の要件
外国人側の要件
自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
道路運送法
貨物自動車運送事業法
貨物利用運送事業法
日本の労働力不足を補うために設けられた「特定技能」制度の対象業種の一つに 自動車運送業 があります。本記事では、自動車運送業における特定技能外国人の受け入れに必要な許認可、研修、試験、免許などの要件 を、業務区分ごとに詳しく解説します。
1. 自動車運送業における特定技能とは?
対象業務
自動車運送業における特定技能は、以下の業務が対象となります。
(1)貨物自動車運送業(トラック運転手など)
(2)旅客自動車運送業(バス・タクシーの運転手)
これらは、試験区分に応じた業務区分という法令の条件範囲で申請し、その結果、以下の類型に応じた許可がされます。
【特定技能1号】自動車運送業3類型:
| 業務区分 | 試験区分 | 可能な業務範囲の条件 |
| トラック運転者 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)及び第一種運転免許 | 事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務全般 |
| タクシー運転者 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)及び第二種運転免許 | 事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務全般 |
| バス運転者 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)及び第二種運転免許 | 事業用自動車(バス)の運転、運転に付随する業務全般 |
特定技能1号の在留資格を取得することで、外国人は上記範囲で業務に従事できます。
特定技能1号の特徴
- 在留期間:通算5年まで(更新可能)
- 家族帯同:不可
- 技能試験・日本語試験:合格が必要
2. 受け入れ企業(特定技能所属機関)の要件
特定技能所属機関に課される主な条件
特定技能外国人を受け入れる企業は、以下の要件を満たす必要があります。
(1)自動車運送業分野特定技能協議会の構成員になること
- 国土交通省が設置する 「自動車運送業分野特定技能協議会」 に加入が必須。
(2)行政機関の調査・指導に協力すること
- 国土交通省や委託を受けた機関の調査に対し、必要な協力を行う義務があります。
(3)適切な事業許認可を取得していること
- 貨物自動車運送事業や道路運送法などに基づく許認可を受けた自動車運送事業者であることが必須。
(4)安全・労働環境に関する認証を取得すること
- 以下のいずれかの認証を取得することが求められます。
- 一般財団法人日本海事協会の運転者職場環境良好度認証制度
- 全国貨物自動車運送適正化事業実施機関による安全性優良事業所の認定
(5)タクシー・バス業務の企業は新任運転者研修を実施すること
- 旅客自動車運送業(タクシー・バス)の場合、新人運転者向けの研修を行うことが義務付けられています。
(6)登録支援機関の選定条件
- 1号特定技能外国人支援計画の実施を委託する場合、協議会の構成員であり、国土交通省や協議会に協力する登録支援機関 に委託する必要があります。
3. 許認可要件(業務区分ごと)
特定技能外国人を受け入れるためには、企業が適切な 事業許認可 を取得している必要があります。業務区分ごとに要件を整理します。
(1)貨物自動車運送業
貨物の輸送を行うためには、「貨物自動車運送事業法」 に基づく以下の許可が必要です。
| 事業区分 | 業務区分 | 許認可権者 |
|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業 | トラック運転者 | 国土交通大臣の許可が必要 |
| 特定貨物自動車運送事業 | トラック運転者 | 国土交通大臣の許可が必要 |
| 貨物軽自動車運送事業 | トラック運転者 | 届出制(許可不要) |
(2)旅客自動車運送業
バスやタクシーの運行を行うには、「道路運送法」 に基づく以下の許可が必要です。
| 事業区分 | 業務区分 | 許認可権者 |
|---|---|---|
| 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー・ハイヤー) | タクシー運転者 | 国土交通大臣の許可が必要 |
| 一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス) | バス運転者 | 国土交通大臣の許可が必要 |
| 特定旅客自動車運送事業(特定の利用者向け) | タクシー運転者 | 国土交通大臣の許可が必要 |
| 貸切バス(観光バス等) | バス運転者 | 国土交通大臣の許可が必要 |
(3)貨物利用運送業
第二種貨物利用運送は可能です。
(4)安全・労働環境の認証
前各号の許認可にプラスで以下のいずれかの認証が必要です。
| 安全等認証の名称 | 実施機関 |
|---|---|
| 働きやすい職場認証制度/ 運転者職場環境良好度認証制度 |
一般財団法人日本海事協会 |
| Gマーク/ 全国貨物自動車運送適正化事業実施機関による安全性優良事業所の認定 |
トラック協会 |
働きやすい職場認証制度(正式名称:「運転者職場環境良好度認証制度」)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk1_000025.html
4. 必要な研修・試験・免許
(1)技能試験
特定技能1号の在留資格を取得するには、以下の 技能試験 に合格する必要があります。
- 自動車運送業特定技能評価試験
- 貨物運送業・旅客運送業それぞれの業務内容に応じた試験が実施される。
(2)日本語試験
業務を遂行するための日本語能力が必要なため、以下のいずれかの試験に合格する必要があります。
- トラック:日本語能力試験(JLPT)N4以上
- タクシー、バス:N3以上
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の前各号レベルの合格
(3)運転免許
特定技能外国人が実際に業務を行うためには、日本の運転免許が必要です。
- 第一種普通自動車運転免許(タクシー・軽貨物等)
- 普通・中型・大型免許(トラック・バス等)
- 第二種普通自動車運転免許(タクシー・バス等)
外国人が免許を取得する場合、外国免許切替制度いわゆる「外免切替」を利用するか、日本の自動車教習所で免許を取得する必要があります。
5. 物流系事業許認可は行政書士に委託
谷島行政書士法人グループは事業許認可に多くの実績があり、自動車運送事業の特定技能外国人雇用企業の要件に必要な物流系許認可もワンストップ対応が可能です。
代表的な物流系許認可では、以下の実績があります。
(1)一般貨物自動車運送事業許可:トラック運送
(2)一般乗用旅客自動車運送事業許可:福祉輸送
(3)第一種貨物利用運送業登録:トラック運送
(4)第二種貨物利用運送業許可:航空、内航、外航の外国人
(5)倉庫業登録その他
6. まとめ
自動車運送業における特定技能外国人の受け入れには、企業・外国人ともに様々な要件を満たす必要があります。
企業側の要件
✅ 特定技能協議会への加入
✅ 適切な事業許認可の取得
✅ 労働環境や安全性に関する認証の取得
✅ (行政書士業務は委託可能だが)自社支援又は登録支援機関の利用
外国人側の要件
✅ 技能試験・日本語試験の合格
✅ 適切な運転免許の取得
特定技能制度を活用することで、自動車運送業の労働力不足を補いながら、外国人労働者の活躍の場を広げることが可能です。
特定技能ビザ申請についてのご相談は、谷島行政書士法人までお問い合わせください。
7. 参照法令
自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針
(2)特定技能所属機関に対して特に課す条件ア 特定技能所属機関は、国土交通省が設置する「自動車運送業分野特定技能協議会」(以下「協議会」という。)の構成員になること。 イ 特定技能所属機関は、協議会に対し必要な協力を行うこと。 ウ 特定技能所属機関は、国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査又は指導に対し、必要な協力を行うこと。 エ 特定技能所属機関は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業(貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第8項に規定する第二種貨物利用運送事業を含む。)を経営する者であること。 オ 特定技能所属機関は、一般財団法人日本海事協会(明治32年11月15日に帝国海事協会という名称で設置された法人をいう。)が実施する運転者職場環境良好度認証制度に基づく認証を受けた者又は全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第43条に規定する全国貨物自動車運送適正化事業実施機関をいう。)が認定する安全性優良事業所を有する者であること。 カ タクシー運送業及びバス運送業における特定技能所属機関は、特定技能1号の在留資格で受け入れる予定の外国人に対し、新任運転者研修を実施すること。 キ 特定技能所属機関は、登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を委託するに当たっては、協議会の構成員となっており、かつ、国土交通省及び協議会に対して必要な協力を行う登録支援機関に委託すること。 https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001846439.pdf |
道路運送法
| (定義)第二条この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。4 この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。 |
貨物自動車運送事業法
| 貨物自動車運送事業法 第二条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。 |
貨物利用運送事業法
| (定義)第二条 この法律において「実運送」とは、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者(以下「実運送事業者」という。)の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。 略7 この法律において「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。8 この法律において「第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)をいう。以下同じ。)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。以下「貨物の集配」という。)とを一貫して行う事業をいう。 |
CATEGORY
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。
- 対応サービス
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他