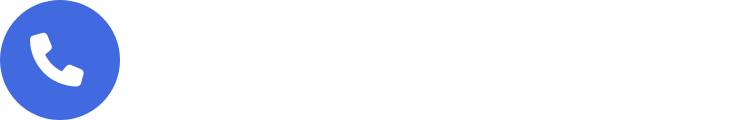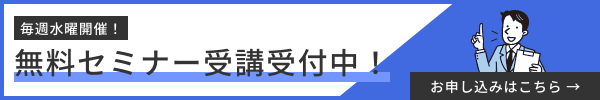在留資格・許可要件の基準適合判定は、申請時点でなく許可処分時か
2025年08月02日
行政法実務許認可
在留資格・許可要件の基準適合判定は、申請時点でなく許可処分時か

内容
行政書士などの許認可手続きに携わる専門家の間で、「許可要件は申請時に満たしていれば良いのか、それとも許可・不許可の処分時に満たしている必要があるのか」というテーマが議論されることがあります。
この問いに対する原則的な答えは、「申請時ではなく、行政庁が許可・不許可を決定する処分時に、許可の基準に適合している必要がある」です。本稿では、この原則とその実務上の影響、そして重要な例外について解説します。
原則:基準適合の判断は「処分時」
多くの許認可申請において、申請者が提出した内容が許可要件を満たしているかを判断する基準時点は、申請書を提出した「申請時」ではなく、審査を終えて行政庁が最終的な判断を下す「処分時」とされています。
これは、行政庁が許可という行政行為を行うその瞬間に、申請者が法に定められた要件を具備していることが論理的な前提となるためです。
この原則がもたらす最も重要な帰結は、不可逆的な影響です。つまり、申請時に全ての要件を完璧に満たしていても、審査期間中に事情が変わり、処分時に要件の一つでも満たさなくなってしまった場合、その申請は不許可となるのが原則です。
この考え方は、在留資格(ビザ)申請だけでなく、様々な許認可手続きに共通しています。例えば、永住許可申請の審査中に、入国管理局(以下、入管)から最新の課税証明書や納税証明書の提出を求められることがあります。これは、処分時(許可時)に至るまで、継続して納税義務などの要件を満たしているかを確認するためであり、この原則から見れば合理的な対応と言えます。
「処分時」原則の具体的な事例:連れ子定住申請
この原則が特にシビアに影響する例として、外国人の「連れ子」を日本に呼び寄せるための在留資格「定住者」の申請が挙げられます。
日本に住む親が、海外にいる子を呼び寄せ、家族で一緒に暮らすために「定住者」の在留資格認定証明書交付申請を行うケースです。この申請では、子が親の「扶養を受ける」ことが重要な要件となります。
実務上、子が18歳以上の場合、自活能力があると見なされ、「扶養を受ける」という要件を満たさないとして不許可となる可能性が高まります。(現行の民法では18歳で成人とされており、判断はより厳しくなる傾向にあります。)
ここで、谷島行政書士法人グループの事例データベースには、次のような事例があります。
- 申請人である子どもが、申請時17歳だったところ、在留資格認定証明書交付時も17歳であるのに、上陸時に誕生日が到来し18歳になるケース
- 申請時の状況: 親が17歳の連れ子のために「定住者」の申請を行う。この時点では年齢要件をクリアしている。
- 審査期間中の変化: 審査には数ヶ月を要することがあり、その間に子が18歳の誕生日を迎えてしまう。
- 処分時の判断: 処分時には子が18歳になっているため、「扶養されるという要件を満たさない」として不許可相当と判断される。
このような状況では、入管の審査官から「このままでは不許可になってしまうため、申請を取り下げてはどうですか」といった、いわゆる「取下げ指導」が行われることがあります。
注意すべきは、上陸時が許可処分時点となります。したがって、在留資格認定証明書交付が17歳でなされてもそのすぐ後に誕生日が到来するため、間に合わないという運用がされました。
これは、入管ないし審査官が人道的に許可を与えたいと考えても、処分時の状況が法の要件を満たさない以上、平等原則もあいまって、許可を出す運用がないためです。
特に在留資格認定証明書交付申請は、裁量をもって要件を加重することもできません。逆に言えば緩和する運用についても可否が硬直的になると考えられます。
なお、入国審査官が、事情を加味して早めの審査をしてくれることは約束されません。申請人のアクションを早くすることが重要なのです。
この事例は、いかに早く申請を行うことが重要であるかを物語っています。
例外:基準適合の判断が「申請時」となるケース(高度専門職)
このように厳格な「処分時」の原則ですが、明確な例外も存在します。その代表例が「高度専門職」の在留資格です。
高度専門職のポイント計算においては、申請者に有利な配慮から、基準時点を「申請時」とする旨が省令で明確に定められています。
| 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(抄) 第一条(高度専門職第一号) 略 2 法第六条第二項、第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)又は第五十条第二項の規定による申請の時点において(中略)前項各号のいずれかに該当する者は、当該申請に係る第一号許可等を受ける時点においてそれぞれ(中略)当該各号に該当する者とみなす。 第二条(高度専門職第二号) 略 2 法第六条第二項、第二十条第二項又は第二十二条の二第二項の規定による申請の時点において前項各号のいずれにも該当する者は、当該申請に係る第二号許可を受ける時点において同項各号のいずれにも該当するものとみなす。 |
この「みなし規定」により、高度専門職の申請では、申請時の状況で要件を満たしていれば、その後の審査期間中に状況が変化しても、引き続き要件を満たしているものとして扱われます。
例えば、高度専門職のポイント計算では年齢が重要な要素となり、20代であれば高いポイントが付与されます。
- 申請時の状況: 29歳で申請し、20代としての年齢ポイントを獲得。
- 審査期間中の変化: 審査中に30歳の誕生日を迎える。
- 処分時の判断: 上記の「みなし規定」により、申請時の29歳として扱われ、20代のポイントが維持される。
このように、高度専門職の制度は、申請者の地位の安定性に配慮し、申請時点の有利な状態を審査の最後まで維持することを法律上認めています。
まとめ
許可要件をいつの時点で満たしているべきかという問いに対しては、以下の通り整理できます。
- 原則: 処分時(許可・不許可の決定時)に要件を満たしている必要がある。審査期間中の状況変化により、不許可となるリスクがある。
- 例外: 高度専門職ビザのように、法律(省令)で特別に申請時を基準とすると定められている場合がある。
この原則と例外を正しく理解することは、許認可申請を成功に導くための重要な鍵となります。特に、年齢や事業年度の経過など、時間の経過によって状況が変わり得る申請においては、審査期間を考慮した上で、一日でも早く手続きに着手することが肝要です。
CATEGORY
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。
- 対応サービス
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
最新の投稿
「行政法実務」関連で人気のコラム
まだデータがありません。