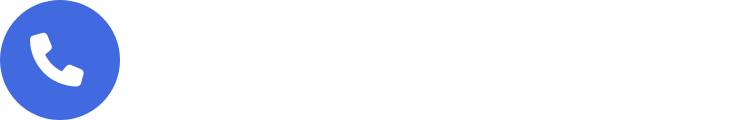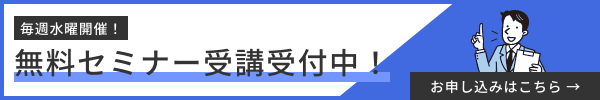技能実習事業のみの事業協同組合|共同事業ゼロの法的リスクを行政書士が解説
2025年08月02日
コンプライアンス技能実習サービス
技能実習事業のみの事業協同組合|共同事業ゼロの法的リスクを行政書士が解説

内容
リスク1:中小企業等協同組合法上の「事業停止」とみなされるリスク
リスク2:技能実習法上の「不適切な監理費」を指摘されるリスク【最重要】
【対策】多くの監理団体は、少額でも共同経済事業を実施している
【はじめに】
外国人技能実習制度の監理団体として事業協同組合を運営されている皆様の中には、日々の業務が技能実習生の受入れと監理に集中し、組合本来の「共同経済事業」(共同購買や共同受注など)が実質的に行われていない、というケースはございませんでしょうか。
周囲から「技能実習事業さえきちんとやっていれば問題ない」と聞き、安心されているかもしれません。しかし、その状態は、将来的に組合の存続を揺るがしかねない、複数の法的リスクを内包している可能性があります。
本記事では、共同経済事業を行っていない組合が直面しうる「3つのリスク」について、専門家の視点から分かりやすく解説します。
リスク1:中小企業等協同組合法上の「事業停止」や「改善命令」
事業協同組合は、その名の通り「中小企業等協同組合法」に基づいて設立された法人です。この法律は、組合が「組合員の相互扶助の精神に基づき、協同して事業を行う」ことを目的としています。
この点、非営利である技能実習生受け入れのみを行い、また最近では、育成就労外国人受け入れ斡旋のみを目的とした組合設立は、趣旨に合わず不適当とされることが多くあります。
つまり、共同経済事業の実績が全くない状態は、この法の趣旨から外れていると見なされる可能性があります。
確かに、共同経済事業を行っていないことだけを理由に、直ちに解散命令(中協法第106条)のような重い処分が下されることは稀です。
しかし、これはリスクがゼロということではありません。所管行政庁(都道府県など)による検査で事業実態の欠如が指摘され、改善命令(法第105条)の対象となる可能性は理論上十分に考えられます。
リスク2:技能実習法上の「不適切な監理費徴収」とされ違反の認定
これが、実務上最も現実的かつ深刻なリスクと言えます。
共同経済事業からの収益がゼロの場合、組合の運営にかかる全ての経費(事務所の家賃、役職員の給与、その他一般管理費など)を、技能実習の「監理費」で賄っていることになります。
ここで重要になるのが、技能実習法第28条の規定です。
| 技能実習法 (監理費) 第二十八条 2 監理団体は、(中略)監理事業に通常必要となる経費等を勘案して主務省令で定める適正な種類及び額の監理費を団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収することができる。 |
組合の運営経費の全てを「監理事業に通常必要となる経費」として、その用途と金額を実習実施者(組合員)に明確に説明し、その妥当性を証明することは、非常に困難な場合があります。
例えば、顧問税理士の報酬まで、監理費から支出することになります。そのような法人会計と言える販売管理費まで徴収する際に用途説明をしている組合は現実的でなく、ほぼ存在しないでしょう。
そうすると、法人会計となるような費用は賄う必要があると考えられます。
実際に、外国人技能実習機構(OTIT)の立入検査では、この監理費の使途の用途明示が事実と異なり又は虚偽であったか、またその妥当性を疑われると、違反の程度が大きい事案として、厳しく審査されます。万が一、「使途が不明瞭」「不適切な監理費の徴収」と判断されれば、指導や改善命令、最悪の場合は監理団体の許可取消しという事態にも繋がりかねません。これは私たちが立入検査の対応支援を行う中でも、実際に直面する重要な問題点です。
事業内容が技能実習のみという偏った運営は、組合内部の対立の火種となる可能性があります。
例えば、一部の組合員から「組合として本来の事業を行っていないではないか」と経営方針を疑問視され、総会で経営陣が糾弾されたり、役員の改選を要求されたりするケースも考えられます。
なお、組合員は、行政庁に処分を求める「不服申出」制度も使うことができます。
組合員との関係性が良好であれば問題は顕在化しないかもしれませんが、将来にわたって無用な内部対立の芽を抱え続けることになります。
私たちの経験上、組合は、たとえ少額であっても何らかの共同経済事業を実施しています。
- ETCコーポレートカード、法人ガソリンカードの共同利用
- 事務用品(アスクル等)やソフトウェアの共同購買
- 組合員向けの経営・労務セミナーの開催(教育情報事業)
こうした事業を行うことで、組合法上の「共同事業の実態」を確保し、同時に、中小企業等協同組合法上及び技能実習法上の「監理費のみが収益」というリスクを回避できます。
「うちは大丈夫だろう」という自己判断が、後々大きな問題に発展することがあります。組合の安全な運営は、適正な技能実習事業を継続していく上での大前提です。
谷島行政書士法人グループでは、監理団体の皆様の現状を丁寧にヒアリングし、各組合の実態に合ったコンプライアンス体制の見直しや、各種法的手続のサポートを行っております。少しでもご不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
CATEGORY
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。
- 対応サービス
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他