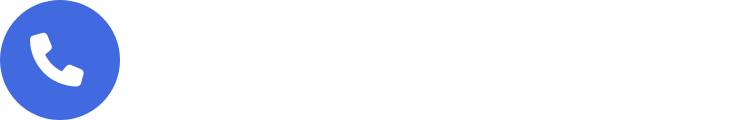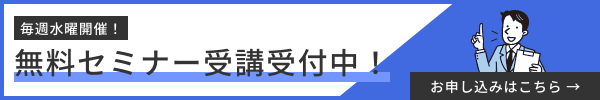特定技能に関する在留申請オンライン手続解説:行政書士と登録支援機関の違い
2025年03月30日
特定活動行政法実務コンプライアンス
特定技能に関する在留申請オンライン手続解説:行政書士と登録支援機関の違い

内容
2.行政書士(申請取次者)によるオンライン手続と登録支援機関による手続の違い
(1) 行政書士:①利用申出不要でオンラインの申請取次可能、②書類作成可能
(3) 登録支援機関:①オンラインの申請取次可能で、②書類作成は不可(違法)
3.「企業ごとに新規の利用申出が必要か」「企業からの依頼書その他資料が必要か」について
|
関連ページ: |
1.特定技能に関する在留諸申請のオンライン手続の概要
特定技能の在留資格に関する手続(在留資格認定証明書交付申請、在留期間更新許可申請等)については、出入国在留管理庁(以下「入管」)が提供している「在留申請オンラインシステム」を利用して電子申請が可能です。
在留申請オンラインシステムは、申請者(企業・個人)または代理人が、オンラインで申請書類や添付資料を提出できる仕組みです。
オンライン申請を行うには、事前に「利用申出」を行い、入管から承認(利用承認)を受ける必要があります。承認を受けると、オンライン申請用の利用者IDが交付されます。
しかし、行政書士はこの利用申出が不要です。
その他、書類作成の手間や、違反になりやすい制約など、特定技能の手続においては、登録支援機関と行政書士とで「在留申請代理」の扱いに大きな差があります。
2.行政書士(申請取次者)によるオンライン手続と登録支援機関による手続の違い
(1) 行政書士:①利用申出不要でオンラインの申請取次可能、②書類作成可能
行政書士は、行政書士法の規定に基づき、「官公署に提出する書類の作成」および「提出手続の代理」を業とすることができます。
この「官公署に提出する書類の作成」は行政書士の独占業務であり、登録支援機関が出入国在留管理局や国土交通省に提出する書類作成を行うと刑罰を受けることになります。
さらに、入管法施行規則に定められた「申請取次制度」を利用することで、在留申請に関する手続を本人に代わって行うことができます。
オンライン申請では利用申出が企業や登録支援機関には必要ですが、行政書士は、企業や外国人から新たに依頼されても利用申出が不要です。したがって、企業や外国人はその手続きを所属機関つまり企業として行う必要がなく、手間をかけずにオンライン申請を行政書士に代理させることができます。
企業からの資料等は、行政書士が申請をする都度、必要に応じて(就労条件を示す資料など)取得することになりますが、行政書士は書類作成代理が可能で「オンライン申請の利用承認」という観点での企業ごとの手続は不要です。
まとめると、行政書士への依頼の場合は、この在留申請オンライン手続の「利用申出」を企業ごとに行う必要もなく、依頼書などの添付資料も企業から頂く必要もありません。他の資料も企業の代理で多くを作成できます。
(2) 行政書士の申請取次の範囲
上記の行政書士法と入管法施行規則の2つの法的根拠に基づき、行政書士は、企業や外国人からの依頼を受け、その企業の雇用する外国人の在留諸申請を代理することができます。さらにワンストップで多くの企業作成資料を代理作成できます。
この代理権限は、特定技能所属機関の定期届と、随時届、その他、外国人が行う届出など全般に及びます。
在留資格でも特定技能に限らず、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「高度専門職」、「永住者」などといった幅広い在留資格に関する申請やあらゆる届出に及びます。
(3) 登録支援機関:①オンラインの申請取次可能で、②書類作成は不可(違法)
登録支援機関は、「特定技能」外国人に対する支援計画の作成や実施などの支援業務を行うことができる機関です。登録支援機関は、生活支援業務が中心であり、支援の中に行政手続の代理権限はありません。
ただし、例外的に、支援先企業で雇用する特定技能1号の在留資格申請に限り、申請取次、つまり提出のみが可能です。
しかし、上記の通り、行政書士法により、行政書士と弁護士以外は、書類作成が業務としてできません。仮に登録支援機関は支援費以外の報酬を受けていないといっても、支援費を書類作成等の報酬と推定されます。
したがって、登録支援機関に支援を委託した場合は、企業自身で書類やオンライン申請フォームを入力する必要があります。
(4) 登録支援機関の申請取次の範囲
登録支援機関の申請取次範囲は、特定技能1号に限定されるという大きな制約があります。特定技能2号やその他の在留資格、定期届出等の申請取次を行うことはできません。
登録支援機関がオンライン申請を行う場合も、まず自分自身が申請を行う主体として入管に利用申出を行い、利用承認を受ける必要があります。
登録支援機関が特定技能1号の申請取次を行うためには、支援業務契約に加えて、企業(受入機関)および外国人本人からの依頼を受ける必要があります。
登録支援機関がオンラインシステムを利用するために、企業ごとに利用申出が必要かどうかは、登録支援機関自身がオンライン申請を行う主体として、すでに入管に利用申出をして利用者IDを取得していれば、そのIDで複数企業の申請が可能です。
ただし、オンラインシステムの利用承認自体を企業ごとに取り直す必要はありません。登録支援機関としての利用者IDを取得していれば、そのIDで複数企業の申請が可能です。
支援業務の範囲(在留申請支援を含むかどうか)や、入管への手続代理の範囲によって、必要な書類(支援委託契約書・依頼書 等)は異なります。
3.「企業ごとに新規の利用申出が必要か」「企業からの依頼書その他資料が必要か」について
(1) オンライン申請システムの利用承認(利用者ID取得)の観点
登録支援機関は、まず自分自身が申請を行う主体として入管に利用申出を行い、利用承認を受ける必要があります。
一方、行政書士は利用申出が不要です。
(2) 支援委託契約の観点
行政書士は、企業や外国人から新たに依頼されても利用申出が不要であるため、企業や外国人はその手続きを所属機関つまり企業として行う必要がなく、手間をかけずにオンライン申請ができます。
登録支援機関の場合は、支援委託契約に加えて、特定技能1号の申請取次を行うための依頼を受ける必要があります。
4.登録支援機関にとって留意すべき主なポイント
- 支援業務契約の明確化: 支援業務契約において、特定技能1号の在留資格申請の支援や取次を含むのかどうかを明確にする必要があります。
- 申請取次権限の限定性: 登録支援機関は、特定技能1号の在留資格申請に限り申請取次が可能であり、その他の在留資格や届出は対象外であることを十分に理解しておく必要があります。
- 書類作成の制限: 登録支援機関は、行政書士の独占業務である「官公署に提出する書類の作成」を行うことはできません。
- 資料の準備・管理: オンライン申請の都度、企業側が用意する就労条件、雇用契約書、支援計画書等の資料を収集し、システムにアップロードする必要があります。
5.在留申請オンライン手続の谷島行政書士法人のサービス
オンライン申請の利用承認(利用者ID)は、登録支援機関は、まず自分自身が申請を行う主体として入管に利用申出を行う手間が生じます。それで利用承認を受ける必要があります。
行政書士は利用申出そのものが不要です。したがって、関連する依頼書等も提出不要です。
行政書士の場合は行政書士法に基づく「官公署への書類作成」という独占業務と、入管法施行規則に基づく申請取次制度を利用できるため、在留申請はオンライン申請も含め、簡易です。
さらに、入管への届出も代理できます。
谷島行政書士法人は、外国人コンプライアンス顧問対応の他、制度開始からオンライン申請を行ってきた経験があり、在留申請業務歴も15年以上の実績があります。
さらに、行政書士なので、特定技能の定期届・随時届などの電子届利用申出も特定技能所属機関の提出から入管からの連絡・調査対応までほとんど代理が可能です。
出典:出入国在留管理庁電子届出システム、https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/i-ens_index.html
お困りの際は是非ご依頼ください。
6. まとめ:在留申請オンライン手続の行政書士と登録支援機関比較
オンライン申請の利用承認(利用者ID)は、登録支援機関は、まず自分自身が申請を行う主体として入管に利用申出を行う手間が生じます。それで利用承認を受ける必要があります。
このため、登録支援機関は、在留諸申請を代理するための依頼や、支援委託契約などの書類は、企業が異なるごとに改めて取り交わしが必要です。
一方、行政書士は利用申出そのものが不要です。
したがって、行政書士なら、コンプライアンスが適合しやすく、専門的であり、また企業も楽です。
一方、登録支援機関の場合、支援委託契約では行政手続は本来含まれません。そのため以下の要件と手間を確認する流れになります。
1. 支援委託契約を交わした企業のみが対象
2. 特定技能1号のみが対象
3. 企業ごとに、別途、利用申出の書類を企業とともに揃える。
4. その中で申請取次の依頼書を受ける。
5. 書類作成は企業が行う必要があるなどの制約の中で手続
上記の通り、在留資格も、登録支援機関は特定技能1号に限定されるのに対し、行政書士は幅広い在留資格の申請取次が可能です。
つまり「特定活動」等も違反となります。
どの立場でオンライン申請を行うかによって必要書類や手続が異なる点に留意してください。
|
関連ページ: |
CATEGORY
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。
- 対応サービス
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他