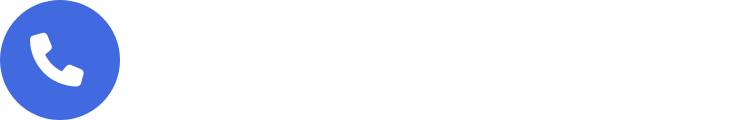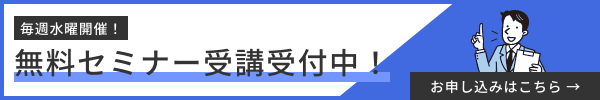育成就労法施行(技能実習廃止)で受入れできなくなる分野、その他企業への影響
2025年03月30日
育成就労技能実習
育成就労法施行(技能実習廃止)で受入れできなくなる分野、その他企業への影響

内容
導入:育成就労へ改正の背景
近年、日本では深刻な人手不足が進行する一方で、国際的な人材獲得競争も激化しています。また、従来の外国人技能実習制度では制度の目的と現場実態の乖離や外国人の権利保護の不十分さといった課題が指摘されてきました。
政府はこうした背景から、外国人にとって魅力的な制度を構築して日本が「選ばれる国」となり、産業を支える人材を安定的に確保する必要があると判断しました。
そこで2024年6月に入管法・技能実習法の改正が行われ、技能実習制度を発展的に解消して新たに「育成就労制度」を創設することとなりました。
この改正で、技能実習法は「育成就労法」に略称も変わります。
この新制度により、これまでの課題解消とともに外国人が日本で就労しながらキャリアアップできる仕組みを整え、長期的に我が国の産業を支える人材を確保することが目指されています。
本ページでは、人事担当者の方向けに技能実習制度の改正内容と新しい育成就労制度のポイントを分かりやすく解説します。
技能実習法改正による育成就労法概要
改正の主な変更点:今回の法改正では、外国人技能実習制度(技能実習1号~3号)の廃止と新在留資格「育成就労」の創設が大きな柱となっています。
従来の技能実習制度が「国際貢献(発展途上国への技能移転)」を目的としていたのに対し、新制度である育成就労制度は「人手不足分野における人材育成と人材確保」を目的としています。
制度目的の違いに伴い、育成就労制度では外国人を労働者として適切に保護します。このため、技能実習制度では制限が大きかった本人の希望による転籍(就労先の変更)が一定の条件下で認められるようになるなど、運用面でも大きな変更が加えられました。
また、技能実習と特定技能制度の連続性が持たせられ、育成就労で必要な技能・日本語能力を身につけた後に特定技能へ円滑に移行できるキャリアパスが整備されます。
これにより外国人が3年間の育成就労を通じて特定技能1号水準の人材へと成長し、その後は特定技能制度の下で引き続き就労できる仕組みが構築されます。
さらに新制度では、監理団体等の管理体制も見直されており、後述するように監理団体は「監理支援機関」という許認可を得ることになり、既存の監理団体も新たな許可が必要となりました。
影響を受ける対象企業:改正の影響を直接受けるのは、これまで技能実習生を受け入れてきた企業や、今後外国人の現場技能者を受け入れようと考えている企業です。新制度で外国人を受け入れるには、その業種が**「雇用可能な育成就労産業分野」に該当している必要があります。
育成就労産業分野とは、特定産業分野(国内人材の確保努力を行ってもなお外国人の受入れが必要な分野)のうち就労を通じて技能を修得させることが適当と認められる産業分野を指し、具体的な対象分野は今後主管省庁による検討を経て政省令で定められます。
現時点の方針では、この育成就労産業分野は特定技能制度の16分野の一部が指定される見込みです。
したがって、自社の業種が対象分野に含まれるか否かで新制度の利用可否が決まります。例えばスーパーマーケットの惣菜職種など現行では技能実習生の受入れが可能だったケースでも、新制度では業種区分上「小売業」に該当して対象外となり受け入れできなくなる場合があります。
今まで特定技能では、スーパーマーケットの標準産業分類が不可能でした。しかし、2024年、スーパーマーケットの標準産業分類の「飲食料品製造業」の特定技能で、販売業務禁止などの条件があるものの、追加されました。したがって、特定技能でスーパーマーケットにおける食品加工業務も可能となりました。
以上から、現在は、育成就労産業分野でも、特定産業分野から選定の可能性がある飲食料品製造業分野の中に、スーパーマーケットの惣菜業務が存在します。
しかし、技能実習で可能だったが特定技能では追加されていない分野も多数あります。
一方で製造業や建設業、農業、介護といった人手不足が深刻な業界は対象分野として引き続き外国人受け入れが可能と見込まれます。
今回の改正法は2024年6月に成立しましたが、施行時期については今後詳細が決定される予定です。現状では国会での手続を経て3年以内、すなわち2027年までの施行が見込まれています。
施行日以降は新規の技能実習計画認定が行えなくなり、新たな受入れは育成就労制度へ移行します。ただし、施行日前に認定申請された技能実習計画については施行日から起算して3か月以内に開始するものであれば従来通り技能実習生の受入れが可能です。
また、施行日時点ですでに在留中の技能実習生は、その認定計画に基づき残存期間は引き続き技能実習を継続できます。
企業はこの移行スケジュールを踏まえ、計画的に対応を進める必要があります。
育成就労法施行で、技能実習受け入れ企業への影響
企業の対応策
新制度への円滑な移行のため、企業は早めに以下の対応策を検討する必要があります。
- 自社業種の確認:まず自社の業種が育成就労産業分野に該当するかを確認しましょう。対象外となる場合、育成就労制度での外国人受入れはできないため、特定技能など他制度の活用を検討する必要があります。
少なくとも、特定産業分野の対象外である企業は早急にご相談ください。
- 現行実習生への対応:現在技能実習生を受け入れている企業は、改正施行まで引き続き現行制度での受入れが可能ですが、施行日以降は新規受入れができなくなるため計画的に準備を進めましょう。
施行直前に駆け込みで実習計画認定申請を行う場合は、遅くても施行日から3ヶ月以内に実習を開始できるかなどを検討します。
既存の実習生については在留期間満了まで受入れを継続しつつ、希望者には特定技能への移行支援などキャリア相談にも応じると良いでしょう。
- 育成就労計画の準備:新制度で受入れを続ける場合、3年間の育成就労計画を作成し認定を受ける必要があります。
計画策定にあたっては、実習内容だけでなく育成目標(習得技能や必要資格)、日本語学習計画、社内指導体制、生活支援体制など総合的な項目を盛り込む必要があります。
早めに情報収集を行い、必要に応じて行政書士等にも相談しながら計画作成に着手しましょう。
- 監理団体との連携:監理団体経由で実習生を受け入れている企業は、その団体が新制度での監理支援機関の許可要件を満たすか確認が必要です。新制度では監理団体に外部監査人設置など厳格な条件が課されるため、場合によっては別の適切な監理支援機関への変更も検討する必要があります。
反対に、自社やグループ会社で直接外国人を受け入れてきた企業(企業単独型)は、今後も単独型育成就労として継続可能ですが、受入れ対象が自社の海外子会社等の社員に限られる点に注意してください。
取引先の外国人を受け入れていた場合は監理型への転換が必要となる可能性が高いです。
- 社内体制の強化:育成就労では外国人労働者の権利保護・支援がより重視されるため、企業内の受入れ体制を見直しましょう。ハラスメント防止や適正な労働条件の遵守はもちろん、労働条件通知書の交付・説明徹底や定期的な面談など、外国人との認識齟齬を防ぐ取り組みが一層重要になります。
転籍希望が出るのは企業にとって人材流出リスクとなるため、日頃から良好な労働環境の維持・待遇改善に努め、「聞いていた話と違う」といった不満が生じないよう配慮することも大切です。
- 試験合格への支援:育成就労外国人が3年後に特定技能へ移行するには所定の技能試験・日本語試験の合格が必要です。
そのため企業はOJTだけでなく、試験対策講座の受講支援や勉強時間の確保、日本語学習教材の提供など、計画的に学習支援を行うことが望まれます。特に日本語能力向上は業務上のコミュニケーション円滑化にも直結するため、社内研修や日本人社員との交流促進によって日常的に学べる環境づくりを検討しましょう。
- 優良認定の活用:技能実習制度同様に、新制度でも適正な受入れを行う優良な受入れ機関に対しては各種手続きの簡素化などインセンティブ措置が講じられる予定です。
例えば申請書類の一部省略などが検討されています。基準を満たす企業は優良認定の取得も視野に入れ、積極的に制度を有効活用すると良いでしょう。
必要な手続きや注意点
新制度施行にあたって企業が留意すべき手続き・ポイントをまとめました。
- 政省令の動向確認:育成就労制度の詳細運用は今後策定される省令・ガイドラインに委ねられています。受入れ可能分野の正式決定、転籍要件の細部、人数枠や試験科目など重要事項が順次公表されるため、入管庁や所管省庁からの発表を定期的にチェックしてください。最新情報の把握が制度移行対応の鍵となります。
- 送出機関の選定:技能実習同様、海外の送出機関選びは重要です。新制度では二国間協力覚書(MOC)締結国からの受入れが原則となり、悪質な送出機関の排除に向けた取組みも強化されます。
信頼できる送出機関を選定し、不当な手数料徴収や虚偽の事前説明が行われていないか確認しましょう。送出国の候補が限られる場合もあるため、必要に応じて複数国・機関を比較検討してリスク分散を図ることも有効です。
- 雇用契約・待遇面:育成就労で受け入れる外国人とは労働契約を締結します。その際の労働条件(賃金や労働時間等)は日本人と同等以上とすること、各種保険への加入、時間外労働の管理など、日本の労働関連法令を確実に遵守してください。技能実習制度下でも最低賃金遵守等は義務でしたが、新制度では労基署との連携強化により一層厳格にチェックされる見込みです。
適正な労務管理は転籍希望の抑止にも繋がります。
- 社内ルール整備:転籍が制度上可能になることで、企業間での人材の奪い合いが懸念されます。自社で育成した人材が他社に流出する事態も想定し、就業規則や社内研修で守秘義務や競業避止に関するルールを再確認・周知しておきましょう。ただし転籍そのものを不当に制限することは認められないため、公序良俗に反しない範囲で合理的な範囲のルール整備に留めます。業界内でも協調して人材の引き抜き防止策を講じることが求められます。
- アフターケア:育成就労期間を満了し特定技能へ移行した元育成就労外国人に対しても、引き続き職業生活上の相談支援が提供される予定です。
育成就労への改正まとめ
技能実習法の改正によって創設される育成就労制度は、技能実習制度の課題を踏まえて大幅に制度設計が見直された新しい外国人受入れ枠組みです。
ポイントを振り返ると、受入れ対象となる「育成就労産業分野」が選定され、3年間の就労を通じた人材育成を行うこと、そして育成後には特定技能制度へスムーズに繋げることで長期雇用につなげる狙いがあります。
また、転籍の条件緩和や監理団体から監理支援機関への移行による管理体制強化など、外国人本人の保護と企業の適正な受入れの両立が図られています。
特に企業単独型技能実習が監理型と単独型に分裂する点は、現行制度で直接受入れを行っていた企業にとって重要な変更点です。人事担当者の方は、自社の状況に照らして新制度への対応準備を進めるとともに、最新情報のアップデートに注視してください。改正後の制度は今後細則が詰められていきますが、基本的な方向性としては「外国人に選ばれる国」を目指してより分かりやすく、魅力的で公正な仕組みを構築することにあります。
適切な理解と準備をもって、新たな育成就労制度を活用し、自社の発展と日本全体の持続的な人材確保につなげていきましょう。
CATEGORY
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。
- 対応サービス
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他