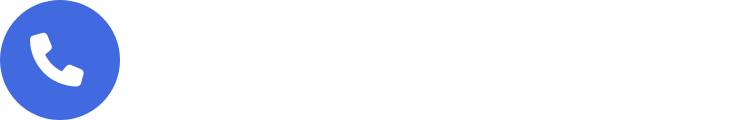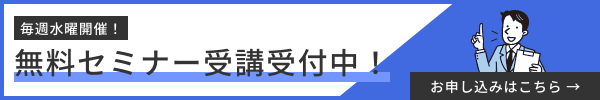育成就労vs技能実習の徹底比較:分野、年数、転籍、監理支援機関、企業単独型
2025年03月17日
育成就労技能実習
育成就労vs技能実習の徹底比較:分野、年数、転籍、監理支援機関、企業単独型

内容
育成就労制度の詳細:分野と職種・作業、転籍
対象産業分野と受入れ要件
技能実習では、幅広い職種・作業が基本的に可能でしたが、3年以上が可能な「移行職種」は91職種168作業(2025年3月時点)が細かく列挙されていました。

出典:外国人技能実習機構
しかし、育成就労制度の対象となる業種は「育成就労産業分野」に限定されます。これは、単に作業職種ベースで受入れを判断していた技能実習制度と異なり、「産業分野」の中で業務区分の観点で受入れ可否が決まることを意味します。
つまり、育成就労の分野の指定は、特定技能制度の対象16分野のうち一部が育成就労産業分野として選定され、そこで外国人の受入れが可能になります。
業種によっては労働者派遣の形態での受入れも認められるため、例えば季節波動のある農業や漁業分野は「労働者派遣等育成就労産業分野」として位置付けられる可能性が高いです。
受入れ企業側の要件も、技能実習制度から一部変更・強化されます。まず受入れには「育成就労計画」の作成・認定が必要で、基本的な手続きの流れ自体は現行の技能実習計画認定とほぼ同様です。
ただし大きな違いとして、技能実習では1号~3号の各段階ごとに計画認定を受けていたものが、育成就労では当初から最長3年間の一貫した計画を作成し一括認定を受ける方式になります。
計画には、従事させる業務内容や達成させる技能レベル、受入れ企業の指導体制、さらには送出機関に支払った費用明細などまで盛り込む必要があり、これらが定められた基準に適合していることが認定要件となります。また在留期間は原則3年間で、人材育成の一貫性確保の観点から途中で業種をまたいだ就労(例:「夏は農業、冬は漁業」等)は認められません。
育成就労で来日する外国人については、入国時点から一定水準の日本語能力(例:日本語能力試験N5程度)が求められる方向です。また原則として家族の帯同は認められない点も技能実習と同様です。
受入れ企業は、計画期間内に当該外国人が特定技能評価試験等に合格し、円滑に特定技能へ移行できるよう、現場でのOJTだけでなく日本語学習や試験対策支援にも取り組むことが間違いなく必要とされます。
転籍/転職(就労先変更)の条件
育成就労制度の大きな特徴の一つが、転籍(受入れ企業の変更)の柔軟化です。現行の技能実習では原則転籍(転職)は認められず、受入れ企業側の都合(倒産等)や法令違反による人権侵害など「やむを得ない事情」がある場合に限り例外的に実習先変更が許可されていました。新制度では、これに加えて本人の希望による転籍も一定の要件の下で認められるとされました。
転籍が可能となるケースは大きく二つあり、①パワハラ・暴力等の被害や契約と実態の重大な不一致などやむを得ない事情がある場合、そして②一定の条件を満たした上で本人の意思で他社への転職を希望する場合です。
つまり育成就労は、「やむを得ない」事情がなくても転職・転籍ができる点が、大きな改正の特徴です。
後者の「本人希望」による転籍が許容されるための転籍の条件として、具体的に以下のような要件が示されています:
- 業務の同一性:転籍先で従事する業務が、現在従事している業務と同一の業務区分であること。
分野をまたぐ転籍は認められません。
- 一定期間の就労:現在の受入れ機関での従事期間が、業種ごとに定められる所定期間(おおむね1年以上~2年以下)を超えていること。
一般的には少なくとも1年以上同じ企業で勤続していれば転籍要件を満たす見込みです。ただし、分野によっては、2年とされます。
- 技能・日本語水準:転籍を希望する外国人本人の技能および日本語能力が一定水準以上であること。
例えば技能検定基礎級や日本語能力試験N5相当以上に合格していること等が条件となる見通しです。
- 受入れ先の適正性:転籍先となる企業(育成就労実施者)が不正行為をしていないことはもちろん、在籍外国人に占める転籍者の割合が一定以下であること、転籍までのあっせん経緯を確認できること等、受入れ先として適切と認められる基準を満たしていること
以上の要件を全て満たした場合に限り、本人都合の転籍が認められるとされます。
具体的な運用詳細は今後の政省令で定められますが、転籍を希望する場合の手続きとしては、まず育成就労外国人から外国人育成就労機構や監理支援機関、現行の受入れ企業に対して転籍の申出を行う仕組みが想定されています
これには届出義務が企業および監理支援機関に生じるとされます。
申出を受けた関係機関は相互に通知を行い、その後監理支援機関が中心となって新たな受入れ企業との間で雇用契約成立のあっせん(職業紹介)を行います
転籍先が決定したら、新しい受入れ先で改めて育成就労計画の認定を受ける必要があります。
なお、安易な人材の引き抜きや過度な転籍の頻発を防ぐため、転籍時の補償制度の導入も検討されています。
具体的には、転籍に際して元の受入れ企業が負担した初期コスト等について、転籍先企業が適切に補償金を支払う仕組みを設ける方向です。
業界ごとの協議会を組織し、モラルに反する引き抜き防止策を講じることも計画されています。
これは、都市部集中をしないことの方策でもあります。
技能実習制度との違い
新旧制度の主な相違点を整理すると以下のとおりです。
- 制度目的:技能実習制度は「開発途上国への技能移転による国際貢献」が目的だったのに対し、育成就労制度は「国内の人手不足分野での人材育成・確保」が目的です。
この目的の違いから、新制度では外国人を労働力として位置付け適切に保護・育成する方向にシフトしています。
- 在留期間とキャリアパス:技能実習生は原則1号・2号・3号を経て最長5年間在留できましたが、新制度の育成就労外国人は原則3年間の就労が上限です。
ただし、試験不合格時などは最大1年の延長可能です。
3年間の育成就労期間を経て、特定技能評価試験等に合格すれば特定技能1号(在留可能期間通算5年)への移行が可能であり、一定の実務経験と更なる試験合格で特定技能2号(在留期限の上限なし・家族帯同可)へ進む道も開かれます。
特定技能2号では、永住許可も目指すことができます。
技能実習でも3号修了者は特定技能1号への在留変更が認められていましたが、新制度では初めから特定技能への移行が前提となっている点が異なります。
- 対象分野・職種:技能実習は91職種・168作業(2025年3月時点)が認められていましたが、新制度では受入れ可能な育成就労産業分野に属する業務に限定されます。
そのため、業種によっては従来可能だった受入れができなくなるケースがあります。
逆に言えば、対象分野内であれば技能実習より幅広い職務で受入れができる可能性もあります(特定技能と同一の分野であるため)。
例えば、建設分野では、技能実習の場合、限定列挙されていた職種が、特定技能では、建設業許可に存在する全てが可能となっております。
この特定産業分野の中から育成就労分野でも包括的に指定されるため、通常、技能実習より広くなるといえます。
- 受入れ要件:技能実習では送り出し国での事前講習(6ヶ月以上または360時間以上)や各段階での技能検定合格(基礎級・3級など)が要件でした。
育成就労では事前講習に代わり又はそれと共に一定の日本語能力(N5程度)が求められる方向で、また来日後1年以内に技能検定基礎級合格といった目標達成が求められます。
また特定技能1号への移行時には日本語能力試験N4相当+技能検定3級または専門級レベルの合格など、技能実習時代と比べ日本語力の重視が顕著です。
加えて、技能実習では受入れ企業の規模に応じた人数枠(常勤職員数に応じ1号は最大5名まで等)が設けられていましたが、新制度でも基本的に受入れ人数枠が適用される見込みです。
さらに特定技能と同様に分野ごとの受入れ枠上限も導入されえます。
- 転籍・転職の可否:技能実習では原則として転籍は禁止され、研修先企業で計画どおり技能を習得して帰国する前提でした。
育成就労では上記のとおり一定の条件下で転籍が可能となり、特に同一企業で1年以上就労した後であれば本人の希望による転職も容認されます
この違いは受入れ企業にとって人材流出リスクとなる一方、外国人本人にとっては就労環境の改善やキャリアアップの選択肢が広がるというメリットがあります。
- 監理・支援体制:技能実習制度下では監理団体(組合等)が実習生の監理を行い、政府は外部機関OTIT(外国人技能実習機構)を設置していました。
育成就労制度では監理団体は「監理支援機関」と名称変更され、その許可要件も厳格化されます。具体的には外部監査人の設置や職員体制・財政基盤・相談対応能力など厳しい基準を満たす団体のみ許可され、機能不十分な団体は排除される方針です。
また監理支援機関が支援業務を他に委託する場合、委託先は登録支援機関(特定技能での支援機関)に限るとされ、支援業務の質向上が図られます。外国人技能実習機構(通称:OTIT)も「外国人育成就労機構」へ改組され、特定技能者の相談支援業務も担いつつ監督指導機能を強化します。
労働基準監督署や入管当局との連携も深め、不正行為の取締り強化や罰則引上げ(不法就労助長罪の厳罰化等)も実施される見込みです。
これらにより従来以上に法令順守と適正な受入れが企業側にも求められることになります。
企業単独型技能実習の単独型・監理型
企業単独型技能実習の大幅改正
企業単独型技能実習は新制度に移行するにあたり監理型育成就労と単独型育成就労に分裂する形になります。
すなわち、海外現地法人の社員を受け入れる場合は監理団体を介さない直接受入れ(単独型)が可能ですが、現地法人を持たず取引先企業の社員を受け入れるケースでは単独型は認められず監理型での受入れとなります。
また、技能実習で行われていたごく短期間の研修的な受入れ(一部の企業単独型1号実習)は、在留資格「企業内転勤2号」での招へいや在留となります。
育成就労産業分野にない業務は企業内転勤2号活用
企業内転勤2号は研修や現場作業が可能です。したがって、企業内転勤2号を併用することで、特定技能につなげない予定の受入だけでなく、育成就労産業分野に存在しない分野も可能となります。
育成就労 vs.技能実習の制度比較まとめ表
以上、育成就労と技能実習の比較を行ってまいりました。さらに次の通り、技能実習制度と新たな育成就労制度の相違点をまとめた比較表をまとめとして示します(※企業単独型の分裂についても含む)。
| 項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |
| 制度目的 | 開発途上国への技能移転による国際貢献 | 人手不足分野での人材育成と人材確保 |
| 在留期間 | 最長5年(1号1年+2号2年+3号2年) | 原則3年(育成期間3年以内)。試験不合格時等は最大+1年延長可 |
| 受入れ分野 | 3年以上可能な「移行職種」は91職種168作業(2025年3月時点) | 特定産業分野の内、育成就労産業分野に属する分野の業務
それ以外は、企業内転勤2号で救済可能か検討 |
| 受入れ人数枠 | 企業規模に応じ上限あり(例:30人以下の常勤社員数なら、1号実習生は3人まで等) | 技能実習と同様に人数枠を設定予定
さらに分野ごとに年間受入れ人数枠を設定 |
| 転籍(転職) | 原則不可(パワハラ、セクハラ等、やむを得ない場合のみ許容) | 一定の要件下で可能(本人希望による転籍も条件次第で可能) |
| 監理の仕組み | 監理団体が支援・指導。外国人技能実習機構(OTIT)が監督 | 監理支援機関(外部監査義務等あり)により支援。 育成就労機構に改組され、機構が監督・転籍支援等を実施。 |
| 企業単独型の扱い | 本社・子会社社員や取引先社員を企業単独型実習生として直接受入れ可能 | 3つに分化:
自社の海外支店・子会社社員は「単独型育成就労」として直接受入れ可。 一方、海外の取引先企業社員の受入れは単独型不可で「監理型育成就労」として監理支援機関経由で受入れ |
育成就労人材紹介と行政書士による外国人雇用顧問
谷島行政書士法人グループでは、育成就労と技能実習の混在時期でも、双方が可能な専門家を有する行政書士法人です。
ビザ手続はもちろん、外国人材紹介から、コンプライアンス顧問まで全てを高いレベルで対応可能です。
育成就労制度は、適切に理解しないとリスクがあります。技能実習と3年以上併存することになり、とても複雑です。
一方で、特定技能や永住までの導線をプランニングすることで永久的な人材確保が可能な制度です。技能実習もしかり、育成就労を利用しないで成り立たない業界は多い現状です。
育成就労に強い行政書士法人をお探しの方や、現場系等の外国人雇用や採用でお困りの方はぜひお声掛けください。
CATEGORY
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。
- 対応サービス
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他