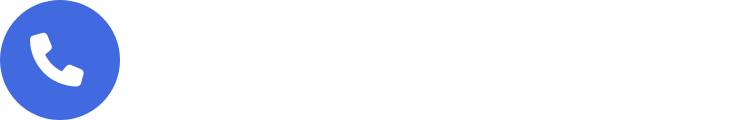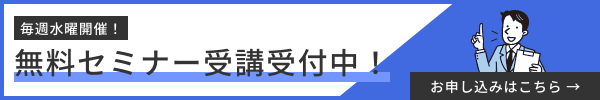飲食料品製造業の特定技能の産業分類など徹底解説
2024年11月01日
飲食料品製造業特定技能
飲食料品製造業の特定技能の産業分類など徹底解説

内容
飲食料品製造業における特定技能制度の概要
日本の飲食料品製造業分野では、深刻な人手不足が続いており、特に即戦力として働ける専門的技能を持つ外国人労働者の確保が求められています。こうした状況を解決するため、「特定技能」の在留資格制度が導入され、飲食料品製造業においては、この制度を通じて外国人労働者の受け入れを推進する方針が定められました。
1. 飲食料品製造業分野での外国人労働者受け入れの目的
飲食料品製造業分野では、生産性向上や国内人材確保の取り組みが進められていますが、それでも労働力不足を解消することは困難です。このため、専門的な技能を持つ外国人労働者を受け入れることで、日本の飲食料品製造業の持続的な存続と発展を図ります。特定技能外国人は、即戦力として現場に従事することが期待され、これにより日本国内での食料品の安定供給が維持されることを目指しています。
2. 特定技能外国人の業務区分と資格や経験
試験合格と特定技能1号の業務区分
特定技能1号の資格取得には、飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験に合格することが求められます。この試験では、食品製造の基本的な衛生知識やHACCP(危害分析重要管理点方式)に基づく作業能力が問われます。また、一定の日本語能力が求められ、「日本語能力試験N4」または「国際交流基金日本語基礎テスト」に合格することが条件となっています。
| 特定技能1号の業務区分 | 特定技能評価試験 | 日本語能力試験 |
| 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保) | 飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験 | 日本語能力試験(N4以上) 又は国際交流基金日本語基礎テスト |
技能実習修了と特定技能1号の業務区分
技能実習2号良好修了のルートもあり、それは以下の職種・作業を良好修了で経ていれば免除となります。
| 特定技能1号の業務区分 | 職種 | 作業 |
| 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び 安全衛生の確保) |
缶詰巻締 | 缶詰巻締 |
| 食鳥処理加工業 | 食鳥処理加工 | |
| 加熱性水産加工食品製造業 | 節類製造、加熱乾製品製造、調味加工品製造、くん製品製造 | |
| 非加熱性水産加工食品製造業 | 塩蔵品製造、乾製品製造、発酵食品製造、調理加工品製造、生食用加工品製造 | |
| 水産練り製品製造 | かまぼこ製品製造 | |
| 牛豚食肉処理加工業 | 牛豚部分肉製造 | |
| ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | ハム・ソーセージ・ベーコン製造 | |
| パン製造 | パン製造 | |
| そう菜製造業 | そう菜加工 | |
| 農産物漬物製造業 | 農産物漬物製造 |
試験合格と経験:特定技能2号の業務区分
特定技能2号は、さらに高い熟練技能や管理を行う能力が求められます。特定技能2号評価試験に加えて、飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験受験までには2名以上(アルバイト、技能実習生や特定技能外国人を含む)を指導しながら作業し、工程管理者としての2年以上の実務経験が必要です。したがって、特定技能1号の在留期間中に適切な管理経験を積むことも要件とされています。
| 特定技能1号の業務区分 | 特定技能評価試験 | 実務経験 |
| 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の
確保)及び当該業務に関する管理業務 |
飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験 | 飲食料品製造業分野において、複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工
程を管理する者としての実務経験 |
3. 受け入れ見込み数と人手不足の状況
今後5年間で、飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受け入れ人数は、最大13万9000人が見込まれています。これは、現在の深刻な人手不足に対応するために計算された人数であり、例えばAIやロボットの導入による生産性向上の努力を続けても、なお外国人労働者の受け入れが不可欠であることが示されています。
2023年時点で、飲食料品製造業の有効求人倍率は3.11倍と、全産業平均を大きく上回っています。
4. 運用の具体的な要領
試験の実施方法
飲食料品製造業特定技能1号・2号技能測定試験は、農林水産省が選定した民間事業者により、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式やペーパーテスト方式で実施されます。試験実施においては、替え玉受験などの不正行為を防ぐための適切な対策が取られています。
日本語能力の確認
特定技能1号外国人は、日本語能力試験N4または国際交流基金日本語基礎テストに合格する必要があります。また、技能実習制度を経て日本語能力を十分に習得したと認められる場合は、日本語試験を免除されることもあります。
労働環境と支援体制
受け入れ機関は、「食品産業特定技能協議会」に参加し、外国人労働者の適正な受け入れや保護に関する情報共有、法令遵守の徹底、不正行為の防止に取り組むことが求められています。また、農林水産省による調査や指導への協力も義務付けられています。
5. 飲食料品製造業の特定技能外国人が従事する業務
特定技能外国人は、飲食料品の製造・加工や安全衛生の確保に「幅広く」従事します。日本人労働者と同様に、関連業務として原料の調達や清掃などにも従事することが可能です。また、特定技能2号外国人は、製造現場での管理業務も担います。
6. 地域分布と治安対策
外国人労働者が都市部に過度に集中しないよう、試験は全国各地で実施されます。特定技能外国人の集中を避け、地方への労働力分散が図られています。また、治安への影響を考慮し、農林水産省は、外国人労働者が関わる犯罪や問題を把握し、必要に応じて事業者に対する指導を行います。引き抜きなどは問題になります。
飲食料品製造業の特定技能特有の受入企業の要件
特定技能外国人を受け入れる企業は、いくつかの要件を満たす必要があります。その中でも主とする日本標準産業分類(日本政府が定めた経済活動の分類)に基づく産業分類は、企業が特定技能外国人を受け入れるための重要な基準の一つです。
1. 「主として行う」標準産業分類とは?
主として行う標準産業分類とは、企業が最も主要な事業として従事している産業分野を指します。企業は複数の事業に関わる場合がありますが、その中でも主として行っている事業が特定の産業分類に該当している必要があります。これが、「主とする標準産業」分類です。
特定技能の飲食料品製造業分野において外国人を受け入れる企業は、企業が主として行う事業が日本標準産業分類で指定された特定の産業分類に該当している必要があります。
2. 主とする標準産業分類における該当する産業
特定技能外国人を受け入れる企業が該当すべき日本標準産業分類は、具体的に以下の産業が指定されています:
| 09 食料品製造業: 飲料、調味料、加工食品などの製造を行う企業。
101 清涼飲料製造業: ソフトドリンクなどの清涼飲料水を製造する企業。 103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く): 茶葉やコーヒー豆などを加工・製造する企業。 104 製氷業: 氷を製造する企業。 5621 総合スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る): 食料品の製造を行うスーパー。製造と販売が一体化している事業。 5811 食料品スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る): 主に食料品の製造を行い、その販売も行うスーパーマーケット。 5861 菓子小売業(製造小売): 菓子を製造し、その場で販売する事業。 5863 パン小売業(製造小売): パンを製造して販売する小売事業。 5896 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(製造小売): 豆腐やかまぼこなどの加工食品を製造して販売する事業。 |
3. 主とする標準産業分類の確認方法
企業が特定技能外国人を受け入れる際には、その企業の事業が上記の日本標準産業分類に該当していることを証明する必要があります。具体的には、以下の点を確認します:
製造業の割合: 事業所全体で、どの産業分類が主に収益を生んでいるかを確認します。例えば、食料品製造を主たる業務としながら、製造と販売が一体化している場合でも、製造部門が主要な事業であることが求められます。
具体的には、売上高が一番高い産業分類が、通常求められます。
4. 主とする標準産業分類の重要性
特定技能外国人の受け入れにあたって、企業が、飲食料品製造業の特定技能で可能な「主とする産業分類」に該当することは、外国人労働者がその企業で法令上適切な職務に従事し、飲食料品製造業の人手不足分野の解決のために重要です。この要件を満たすことで、特定技能外国人が本来の資格にふさわしい業務に従事でき、受け入れの目的が達成されることが保証されます。
その他の飲食料品製造業の特定技能の注意点
企業が特定技能外国人を受け入れる場合、上記の「日本標準産業分類」に該当するだけでなく、他にも以下の点に注意が必要です:
1. 雇用形態: 特定技能外国人の雇用は直接雇用に限られ、派遣労働は認められていません。
2. 支援体制: 企業は、外国人労働者が適切な支援を受けられるよう、農林水産省の協議会に加入し、法令に基づく支援計画を策定する必要があります。
登録支援機関に委託する場合は、登録支援機関も協議会に加入する必要があります。
3. 特定技能外国人の業務区分:飲食料品製造業の特定技能外国人は、仕入れなどの「関連業務」のほか、日本人が通常従事する場合は、製造・加工・販売が密接不可分である場合に、「付随業務」で可能です。
a. 関連業務である付随業務:
原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理作業等
b.関連業務でない付随業務:
日本人が通常従事する場合、かつ製造・加工・販売が密接不可分である場合の販売等の業務
ただしスーパーマーケットにおいては、販売が禁止されている例外があるので、注意が必要です。
| 特定技能受入のための分野別運用要領抜粋:飲食料品製造業
総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)及び食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。) 以外の産業については、同一事業所内において製造・加工・販売が密接不可分の場合は、 日本人が通常従事することとなる販売業務に付随的に従事することは差し支えない。 |
飲食料品製造業特定技能のキャリアアッププラン
特定技能外国人を受け入れる企業は、単に労働力を確保するだけでなく、適切な支援と管理体制を整える必要があります。その中でも重要な要件の一つとして、キャリアアッププランの提示・説明があります。この要件について詳しく説明します。
①キャリアアッププランの提示・説明の義務
企業は、特定技能外国人と雇用契約を締結する前に、その外国人が将来的にどのようなキャリアパスを描けるかという「キャリアアッププラン」のイメージを事前に示さなければなりません。具体的には、次の手順が必要です:
キャリアアッププランの設定: 特定技能外国人が就労を通じて、どのようにスキルを向上させ、将来的にどのような役職や業務に携わる可能性があるかを具体的に設定します。
書面または電磁的記録による提供: 雇用契約を締結する前に、キャリアアッププランを説明した書面を外国人労働者に交付するか、もしくは電子データで提供します。この際、十分な理解が得られるように説明を行うことが求められます。
②飲食料品製造業特定技能のキャリアアッププランの具体例
飲食料品製造業においては、例えば、次のようなキャリアアッププランが考えられます。
・入社時: 基本的な飲食料品の製造・加工業務に従事し、製品の安全衛生管理に関する知識を深める。
・2年目以降: 熟練度が増すにつれ、より専門的な業務や機械の操作を担当。また、他の従業員の指導や管理業務に携わる。
・4年目以降: 2年の指導・作業・管理の実務経験を積み、特定技能2号に移行後、より現場での管理業務を任される。
・それ以上の長期:さらに、日本語検定のN2やN1等に挑戦し、合格とともにリーダーシップを要する複数チームの統括役職に就くことで昇給と昇格を果たす。
上記は、運用要領における以下の要素を組み込んでおります。
| 特定技能受入のための分野別運用要領抜粋:飲食料品製造業
【キャリアアッププランの内容の例】 ※任意様式 ・ 想定されるキャリアルート ・ 各レベルの業務内容及び習熟の目安となる年数 |
③企業側の対応と重要なポイント
企業は、キャリアアッププランを提供するにあたって、以下の点を重視する必要があります:
現実的かつ具体的なプランの提示:
キャリアアッププランは、外国人労働者が実際に経験できる成長過程に基づいている必要があります。過度に理想的なプランではなく、現場の実情に即した現実的な成長パスを描くことが求められます。
定期的な見直しと支援:
プランは雇用契約時に提供されますが、その後も定期的に進捗を確認し、必要に応じて見直しや追加支援を行うことが望ましいです。これにより、労働者が実際にキャリアアップを実現できるように支援します。
コミュニケーション:
キャリアアッププランの説明は、労働者の言語能力や理解度を考慮し、丁寧に行うことが必要です。特に外国人労働者にとっては、言語や文化の違いがあるため、十分に理解されることが重要です。
CATEGORY
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。
- 対応サービス
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他
「飲食料品製造業」関連で人気のコラム
まだデータがありません。