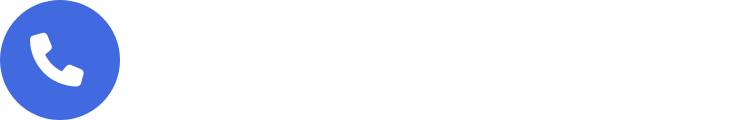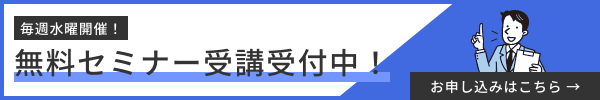自動車運送業の特定技能外国人の業務区分、受入れ企業の要件、申請の流れ等全て解説
2025年03月15日
特定活動特定技能
自動車運送業の特定技能外国人の業務区分、受入れ企業の要件、申請の流れ等全て解説

内容
5. 自動車運送業の特定技能又は「特定活動55号」在留申請・手続の流れ
1.自動車運送業の特定技能、その業務区分
「特定技能」は深刻な人手不足が生じている特定産業分野において、一定の専門性や技能を持った外国人が就労できる在留資格制度です。その中で、自動車運送業は 物流・運送分野の人手不足を補うため、特定技能の対象業種として追加されました。
試験区分に対応する業務区分の範囲で許可されるため、それぞれの区分で申請を行い許可される必要があります。その対象となる業務区分は以下の通りです。
- トラックドライバー(貨物運送)
- バスドライバー(乗合旅客運送)
- タクシードライバー(一般乗用旅客運送)
なお、鉄道運送は別の特定技能分野で可能です。
2. 自動車運送業の特定技能運用方針
国土交通省の「自動車運送事業の特定技能外国人受入れに関する運用方針(令和2年10月1日)」によると、受入れ事業者は以下のような要件・方針を満たす必要があります。
(1)安全対策の徹底
- 道路交通法や各種安全基準を順守
- 必要な研修や教育体制の整備
(2)適切な雇用環境の確保
- 外国人ドライバーへの適切な給与・労働条件の保証
- 就労環境改善や福利厚生の整備
(3)日本語能力や技術水準
- 特定技能として求められる日本語能力試験・技能試験への合格
- 業務遂行に必要なコミュニケーション能力の確保
(4)行政への在留許可申請、報告・届出
- 出入国在留管理局への在留資格手続き
- 出入国在留管理局への届出・報告義務
運用方針の詳細は、法務省のPDF をご参照ください。
3. 自動車運送業の特定技能外国人雇用のメリット・課題
メリット
- 人手不足解消
物流や旅客運送など慢性的な人手不足を補える - 多様性の促進
社内・業界の国際化が進み、業務品質の向上が期待できる
課題
- 安全確保
長距離・長時間運転という業務特性上、安全教育・研修が欠かせない - コミュニケーション面
運行管理者とのやり取りや事故対応で、十分な日本語能力が必須 - 居住・生活サポート
地方勤務などの場合は、生活環境の整備や支援体制を整える必要がある
4. 自動車運送業の特定技能の業務区分・試験区分
特定技能外国人を採用するには、該当する特定技能評価試験と日本語試験に合格していることが必須です。
試験区分がトラック、タクシーあるいはバスなどの業務区分に対応しております。免許等も業務区分によって異なるため、別の解説ページで詳しく説明しております。あらかじめ確認が必要です。
⇒特定技能の自動車運送業に必要な免許、許認可、研修、試験等:業務区分ごとに解説
- 日本語試験:以下のいずれか
- トラック運送:「日本語能力試験(JLPT)」N4以上
- タクシー、バス運送:N3以上
- 「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」の同一レベル合格
- 技能試験(業種別の試験)
- 自動車運送業に関する実務知識や運転技術を評価する特定技能評価試験:
すでに外国で実施済
- 自動車運送業に関する実務知識や運転技術を評価する特定技能評価試験:
なお、自動車運送業の特定技能1号での在留は最長5年、特定技能2号への移行は現時点(執筆時)では自動車運送業は対象外ですので、 5年間が上限となります。
5. 自動車運送業の特定技能又は「特定活動55号」在留申請・手続の流れ
主な申請フロー
(1)受入れ企業の要件確認
- 安全対策・労働条件の整備、支援計画の策定が可能か確認
(2)技能試験・日本語試験の合格証明取得
- 外国人本人が受験し、合格証明書を取得
(3)雇用契約の締結
- 給与・労働条件等を定めた契約締結
(4)在留資格認定証明書交付申請
- 出入国在留管理局に必要書類を提出
(5)日本の自動車運転免許の有無;タクシー、バスの場合の新任運転手研修
a. 日本の運転免許がある場合:「特定技能1号」在留資格認定証明書の取得を経て日本へ入国
b. 日本の自動車運転免許がない場合:「特定活動55号」在留資格認定証明書の取得を経て日本へ入国
c. タクシー、バスの新任運転手研修を受ける場合:「特定活動55号」在留資格認定証明書の取得を経て日本へ入国
(6)入管申請をした結果の認定証明書を海外の日本大使館等に提出し、ビザ申請・発給を受ける
必要書類の例
- 合格証明書(日本語試験・技能試験)
- 雇用契約書
- 受入れ企業の概要資料・決算書類等
- 支援計画書(自社で行う場合 or 登録支援機関との委託契約のいずれも自社作成が必要)
- その他
上記の特定活動かどうかなど、個別事情で異なるためご相談ください。
6.雇用企業の受入れ基準:自動車運送業の特定技能
特定技能外国人を受け入れる自動車運送事業者は、下記のような要件を満たすことが必要とされています。特に事業許認可は複雑なため、別のページで詳しく解説します。
⇒特定技能の自動車運送業に必要な免許、許認可、研修、試験等:業務区分ごとに解説
(1)一定の事業許認可等
- 貨物自動車運送事業、旅客自動車運送事業などの許可+Gマークなど
- 運行管理者を配置し、安全教育を実施
(2)労働条件の明示・適正な給与水準
- 例:日本人と同等以上の報酬を支払う
(3)支援体制の整備
- 生活オリエンテーションや住居確保等の支援計画
- 受け入れ企業自ら行う場合は登録支援機関不要だが、専門知識がない場合は委託が望ましい
(4)行政への定期・随時報告義務
- 出入国在留管理庁への定期届、随時届
(5)その他多数の要件
- 財務、日本人の離職その他
7.支援計画:自動車運送業の特定技能
自動車運送業で働く外国人が 安心・安全に日本で生活・就労できるよう、受入れ企業は支援計画を策定することが義務付けられています。主な支援内容は以下の通りです。
- 生活オリエンテーション
日本でのルールや生活習慣、交通法規の説明 - 住宅の確保
社宅やアパートの斡旋、契約時の保証人サポート - 行政手続きの補助
在留カード、市区町村役場での住民登録、銀行口座開設など - 日本語学習支援
業務上必要となる専門用語を含めた学習支援
登録支援機関へ業務を委託する場合は、契約書を締結し、適正な支援が行われるよう監督する必要があります。たまに誤解がありますが、登録支援機関による支援の不備があると、登録支援機関が処分されることはもとより、所属機関が主として処分されるため、身代わりにはなりません。
8. 給与・待遇:自動車運送業の特定技能
受け入れ企業は、特定技能外国人に対し 日本人と同等以上の給与水準を保証しなければなりません。また、時間外労働や休日手当、各種保険(社会保険・労働保険)の適用も日本人と同等に行う必要があります。
- 給与相場
運転業務の場合、基本給+各種手当の合計で同職種の日本人と同等以上 - 就業時間・休日
法令に基づき労働時間を設定し、過度な長時間労働を避ける - 福利厚生
健康保険・厚生年金・雇用保険への加入など
9. 必要書類:自動車運送業の特定技能
在留資格申請や受入れにあたり、以下の書類が代表的に必要となります。
(1)在留資格認定証明書交付申請書又は変更許可申請書
(2)写真(4cm×3cm)
(3)雇用契約書写し
(4)支援計画書
(5)受入れ企業の登記事項証明書、決算内容の概要書
(6)自動車運送業の特定技能評価試験合格証明、日本語試験合格証明
(7)その他、所属機関ごとに異なる資料:納税、社会保険の証明書など
状況によって追加書類が求められる場合があるため、最新の入国管理局・国土交通省の情報を確認してください。
10. 更新・在留期間:自動車運送業の特定技能
- 特定技能1号の在留期間:1年・6か月または4か月(更新可能)
上限は通算5年まで - 更新時のポイント
- 引き続き雇用契約が有効であること
- 賃金や労働条件が適正に維持されていること
- 受入れ企業の要件に変化がないこと
現時点(令和7年3月14日時点)の運用では、自動車運送業は 特定技能2号へ移行できない業種 となっています。そのため、通算5年が実質的な就労上限となります。
行政書士法人によるサポート
谷島行政書士法人グループでは、特定技能外国人の受け入れを検討される自動車運送事業者様に以下のようなサポートを提供しております。
- 在留資格申請書類作成・提出代行
- 専門家による書類のチェックと申請手続きの一括代行
- 支援計画の策定支援
- 自社支援か登録支援機関の活用かの検討・支援内容の整備
- 試験情報の提供・外国人材採用サポート
- 日本語・技能試験の最新情報、採用手法のアドバイス
- コンプライアンス支援・顧問契約
- 入管・国土交通省・労働関連法令への対応
自動車運送業における外国人材の採用をご検討の際は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。最新の法改正・運用方針を踏まえ、適切なサポートをいたします。
まとめ
特定技能「自動車運送業」は、 人手不足対策の一環 として期待される反面、 安全対策や適切な雇用管理 が求められる分野です。国土交通省の運用方針や入管法令に準拠し、適正な手続きを行うことが必要不可欠です。外国人材の採用から在留資格申請、支援体制の整備まで、専門家のサポートを活用しながら進めることで、企業にとっても外国人材にとっても最良の結果につなげられます。
CATEGORY
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。
- 対応サービス
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他