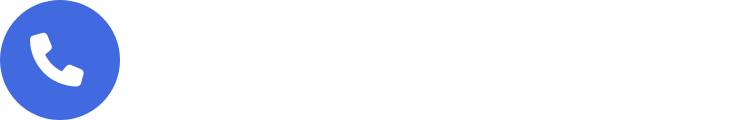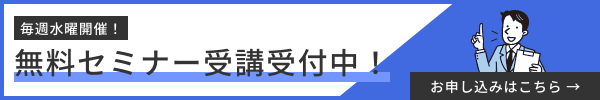自動車運送特定技能の準備「特定活動55号」で外免切替、新任運転者研修
2025年03月15日
特定活動
自動車運送特定技能の準備「特定活動55号」で外免切替、新任運転者研修

目次
1-1.在留資格「特定活動」とは
1-2.背景と目的
1-3.在留期間
2-1.受入れ企業(所属機関)の基準
2-2.外国人本人の基準
3-1.雇用契約で行うことができる活動
3-2.就労できる活動
6-1.特定技能1号移行の流れ
6-2.注意事項
8-1. 受入れ企業の産業分類
8-2. 受入れ企業や支援の基準、届出(特定技能基準省令に準ずる特定自動車運送業準備基準告示)
1.特定活動告示55号とは?
1-1.在留資格「特定活動」とは
「特定活動」とは、法務大臣が個別に告示する活動内容に従って日本での在留を認める在留資格で、さまざまな目的に対応するために、それぞれが実質別の在留資格となる類型があります。
特定活動の告示55号は、その中でも自動車運送業における運転業務に就くことを目的とした外国人が、必要な免許や新任運転者研修をクリアするための特定活動として位置づけられます。
これは「特定自動車運送業準備特定活動」という名称で、他の特定活動と法令上区分されます。
1-2.背景と目的
自動車運送業の人手不足が深刻化する中、免許制度などにより、すぐに運転業務に就ける技能水準に達していない外国人であっても、「日本の運転免許取得」、「所定の研修(新任運転者研修など)」を受講する期間を設け、その後に特定技能などへスムーズに移行する道を整備するのが告示55号の狙いです。
1-3.在留期間
可能な在留期間は貨物運送と旅客運送で異なります。以下、自動車運送業特定技能1号の業務区分にしたがって列挙します。
- トラックドライバーの特定活動:6か月
- バスドライバーの特定活動:1年
- タクシードライバーの特定活動:1年
この違いは、それぞれの活動に違いがあるからです。
トラックの場合、外免切替など日本の運転免許取得が必要な期間であるためです。
一方で、バス・タクシーは新任運転研修があることによります。
いずれも上記の6か月や1年の在留期間は更新できません。特定技能1号への移行が前提だからです。
なお、特定技能1号への移行をしても、特定技能1号の通算5年の中に、上記6か月や1年は含まれず、フルで5年の就労が可能です。
2.特定自動車運送業準備の受入れ基準
特定活動告示55号の在留資格で外国人を受け入れる際、受入れ企業(所属機関)と外国人本人の双方に一定の基準が求められます。
2-1.受入れ企業(所属機関)の基準
(1)事業許可
貨物自動車運送事業、旅客自動車運送事業などを適正に行うための許可を有していること。
貨物はトラック運送、旅客はバス運送やタクシー運送が代表的です。
貨物では、代表的な一般貨物自動車運送事業だけでなく第二種利用運送の許認可でも可能です。
さらに、貨物軽運送事業も含まれます。
(2)Gマーク等の適切な安全許認可
外国人を運転者として受け入れる前に、研修段階であっても安全管理・事故防止に必要な体制を整備し、指導監督を行えること。
この基準は許認可に準ずるGマークなどが必要です。このため、軽貨物のみの事業では取得困難です。
(3)生活支援・学習支援
外国人が日本の運転免許を取得するために必要な学習支援体制や、新任運転者研修を受ける際のサポート体制を確保していること。
(4)経営の安定性
外国人受け入れに伴う費用や研修費などを適切に負担できる、十分な経営基盤を有していることが望ましいとされています。
2-2.外国人本人の基準
(1)運転免許を取得する意志・見込み
告示55号の在留資格を得る目的が「日本で運転免許を取得・切替し、運送業の運転者として働く」ことであるため、免許取得が見込まれることが前提となります。
(2)特定技能1号の業務区分に対応する特定技能評価試験合格
具体的には、以下の通りです。
a.トラックドライバー
自動車運送業分野特定技能1号評価試験:トラック区分
b.タクシードライバー
自動車運送業分野特定技能1号評価試験:タクシー区分
c.バスドライバー
自動車運送業分野特定技能1号評価試験:バス区分
(3)基本的な日本語能力
運転免許試験の筆記試験や、研修時の講習内容を理解できる程度の日本語力が必要です。具体的には、以下の通りです。
a.トラックドライバー:日常会話レベル(日本語能力試験N4相当)以上
b.バスドライバー、タクシードライバー:日本語能力試験N3相当以上
(4)業務区分に応じた特定技能1号評価試験と日本語試験の表
2025年2月現在、まだ特定技能2号はありません。特定技能1号は以下の通り、業務区分に応じた試験区分があり、トラック、タクシー、バスの3種類に分かれます。
出典:入管庁、https://www.moj.go.jp/isa/content/001429359.pdf
3.特定活動55号で可能な活動:免許取得、新任運転者研修
3-1.雇用契約で行うことができる活動
特定活動告示55号で在留する外国人は、以下のような活動が認められます。大きく分けて「免許取得等に係る活動」と「新任運転者研修等に係る活動」の2種類があります。
(1)日本の運転免許取得のための学習・試験受験
- 自動車教習所や運転免許センターで教習や試験を受ける
- 外国免許から日本の免許へ切り替える場合の手続きサポートを受ける
(2)新任運転者研修の受講
- バス・タクシーは新任運転者研修を実施
- 安全運行や交通法規、接客(乗客対応)などの実務を学ぶ
(3)在留中の生活支援・日本語学習
- 生活環境に慣れるための学習や支援活動
- 企業内外での日本語教育講座や補習など
特定活動告示55号の在留期間中は、新任研修などの一環として運転実習等を行うことは認められますが、実際に営業運行に乗務し、フルタイムで収益活動を行うには「特定技能1号」など別の在留資格への移行が必要になります。
3-2.就労できる活動
関連業務として以下の職務が可能です。
(1)清掃
(2)片付けなど
4.外免切替手続
海外で取得した運転免許証を、日本国内で有効な運転免許証に切り替える手続き(外免切替)は、告示55号の在留資格取得者にとって重要なステップです。主な手順は以下のとおりです。
(1)必要書類の準備
- 外国免許証
- 外国免許証取得時からその国に通算3ヶ月以上滞在していたことを証明する書類(パスポートなど)
- 翻訳文(JAFや該当国大使館などの公的機関によるもの)
- 在留カードなどの身分証明書
(2)運転免許試験場での申請・適性検査
- 居住地の都道府県にある運転免許試験場で切替申請
- 視力・聴力などの適性検査を受検する
(3)知識確認(筆記テスト)・技能確認(実技試験)
- 日本の交通ルールに関する簡易な筆記試験
- 運転実技試験(コース走行など)
(4)免許交付
- 上記のテストに合格すれば、日本の運転免許証が交付される
ポイント
国や免許証の種類によっては、実技試験や筆記試験が免除される場合があります(例:特定の条約国・地域)。ただし、実地試験や筆記試験が必要となる国も多く、日本語での受検が基本のため、事前の学習サポートが重要です。
5.新任運転者研修修了までの流れ
自動車運送業の運転者として本格的に乗務するためには、事業者が実施する新任運転者研修を修了する必要があります。告示55号の期間中に、この研修を受けることで安全運行や法令の基礎を身につけられるのが特徴です。
(1)企業内研修の実施計画
- 企業が事前に研修カリキュラムを作成
- 運行管理の基本、事故防止策、接遇マナーなどを含む
(2)座学と実務演習
- 座学:道路交通法令、運行管理者との連携方法、健康管理など
- 実務演習:車両点検、乗降介助(旅客事業の場合)、荷役作業(貨物事業の場合)など
(3)安全教育プログラムの受講
- 運転における危険予知訓練(KYT)
- 日本特有の交通ルールや標識の理解(高速道路、冬道など状況別の注意点)
(4)実地訓練(路上実習)
- 運転免許取得後、指導員の同乗のもとで実際のルートを走行
- 無事故・無違反で乗務できるよう習熟度を確認
(5)修了評価
- 研修期間終了後、研修内容の理解度や安全意識などを評価
- 合格となった場合、正式に乗務が可能となる
6.特定技能1号への移行
告示55号での滞在は、あくまで研修や免許取得のための準備段階です。実際に運転業務に従事して報酬を得るためには、特定技能1号など別の就労可能な在留資格へ変更する必要があります。
6-1.特定技能1号移行の流れ
(1)要件確認
- 技能試験(自動車運送業特定技能評価試験等)と日本語試験(例:JLPT N4以上)に合格する必要があります。
- また、日本の運転免許取得をすでに完了していること。
(2)在留資格変更申請
- 「特定活動(告示55号)」→「特定技能1号」への変更申請を出入国在留管理局に提出
- 雇用先企業の雇用契約書、受入れ体制に関する書類、技能試験合格証明などを添付
(3)審査・結果通知
- 出入国在留管理局で審査が行われ、問題がなければ特定技能1号の在留資格が許可される
- 在留カードの変更手続を行う
(4)特定技能1号としての就労開始
- 受け入れ企業で正式に乗務員として就労が可能
- 賃金体系は日本人と同等以上であることなど、特定技能1号のルールを遵守
6-2.注意事項
- 在留期間の制限
特定技能1号は原則5年が上限です。 - 家族の帯同
特定技能2号と異なり、1号では原則家族の帯同は認められません。 - 継続的な支援義務
特定技能1号に移行した後も、企業は外国人に対して生活支援や日本語学習サポートなどを行う義務があります。
7.留学や家族滞在の変更で特定活動55号が不要なケース
留学や家族滞在の在留資格では、包括的な資格外活動許可が得られます。これにより日本の運転免許取得を目指しながら就労することも可能です。すでに免許取得している場合は、ドライバーとしても稼働できます。
バスやタクシーの場合は、新任運転者研修を修了すればよいです。
ただし、留学や家族滞在はあくまで週28時間以内の資格外活動許可範囲となります。
したがって、フルタイムで稼働する場合に特定技能1号への移行を直接、つまり在留資格変更許可申請をダイレクトに行うこともできます。
8. 特定自動車運送業準備の特定活動の規制
8-1. 受入れ企業の産業分類
専業の運送会社はもとより、建設業などの兼業でやっている運送事業者も含めて、事業所の産業分類に該当すれば可能です。
(1)中分類43 道路旅客運送業
(2)中分類44 道路貨物運送業
8-2. 受入れ企業や支援の基準、届出(特定技能基準省令に準ずる特定自動車運送業準備基準告示)
特定技能1号とほぼ同じ規制があります。
離職や債務超過等の基準も同じです。
しかし、この特定活動でも届出義務にかわる報告義務が生じる点が特徴です。これにより随時届の義務があります。
また、タクシーとバス運送業では、必ず新任運転者研修を実施させる義務も運用方針で上乗せとなっております。
9. 法規制と人材選定:行政書士による解決
特定活動告示55号は、自動車運送業における外国人受入れを、特定技能と連続的に可能とする便利な制度です。
しかし、規制や手続きが複雑であるため、多くの自動車運送業者が手探りである現状です。
ご不安があれば、谷島行政書士法人グループにご相談ください。最新のガイドラインや運用状況に合わせたスムーズな受入れ体制を構築いたします。
さらには、グループ法人で人材紹介も可能です。
10. まとめ
特定活動告示55号は、自動車運送業における外国人受入れを段階的に進めるための大変重要な枠組みです。以下のポイントを押さえながら、適切に運用することが求められます。
(1)受入れ基準
- 企業側は運行管理体制や研修計画を整備し、外国人本人は日本の運転免許取得や日本語学習に意欲を持つことが前提。
(2)可能な活動
- 日本の免許取得や新任運転者研修の受講など、あくまで将来の運転業務に向けた準備段階の活動が中心。
(3)外免切替手続
- 海外免許を持っている場合は、試験場での筆記・実技試験や必要書類の準備が鍵となる。
(4)新任運転者研修修了までの流れ
- 座学や実務演習、安全教育、路上実習を通じて、日本の運送業で求められる知識・技能を身につける。
(5)特定技能1号への移行
- 研修や免許取得を終えたら、特定技能の要件(技能試験合格・日本語試験合格など)を満たし、在留資格変更申請を行う必要がある。
特定活動告示55号は、“今すぐ即戦力の運転手としては至らないが、一定期間の研修や免許取得で活躍が期待でき、関連業務が可能な”「特定自動車運送業準備外国人」を受け入れる制度です。
企業としては、将来の特定技能1号への移行を見据えた長期的な雇用計画を立てるとともに、受入れ時点から研修・学習サポートを着実に行うことが成功のカギとなります。
ぜひ谷島行政書士法人グループにご相談ください。
CATEGORY
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。
- 対応サービス
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他