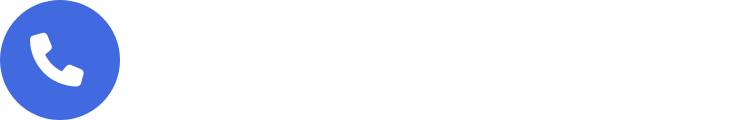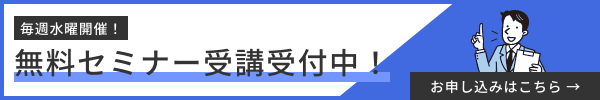申請書の処分歴と在留資格取消しリスク【理論編】:交通違反罰金と虚偽記載
2025年09月25日
在留資格一般
申請書の処分歴と在留資格取消しリスク【理論編】:交通違反罰金と虚偽記載

在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請書には「犯罪を理由とする処分(※交通違反等による処分を含む)の有無」の自己申告欄があります。ここでポイントになるのは、「罰金(刑事処分)」と「反則金(秩序罰)」、そしてその「起訴」や「不起訴(公訴提起なし)」の法的な違いです。ここでは主に日本の法制度で説明します。
内容
(3)(1)又は(2)に該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合
6. 「偽りその他不正の手段(2号)」と「虚偽申請(3号)」の違い
1. 結論の要約
在留資格の申請書に、処分歴記載欄があります。これは交通違反を含むとされております。
| 在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請の申請書 項番15 「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無 (日本国外におけるものを含む。)※交通違反等による処分を含む。」 |
しかし、これは刑事処分のことを主とされております。したがって、反則金(過料)の記載は不要であると考えられ、故意と評価される、入管法における「偽りその他不正」とされる虚偽の記載ではありません。すなわち、「無」としていても、通常、申告漏れとはいえないことになります。
例えば、過去に日本や外国において、スピード違反で罰金刑を受けていれば刑事処分歴に該当し、処分歴「有」となります。
一方で、不起訴で罰金も科されていないなら、同欄は原則「無」で整合し、これを理由に在留資格取消し(22条の4)へ直結する蓋然性は低いと整理できます。もっとも、送致歴等で審査側に疑問が生じ得るため、任意の説明書で事実経過を申出すると安全度が上がります。
しかし、刑事処分でない場合でもすべて書かないと不実記載であると評価されることで「不実の記載」扱いとされることはありえます。もちろん、申請書において過料を含む解釈をされるとは、通常可能性が低いことにかわりありません。
もう一つ、別の要件として、「素行善良」と言えないと評価されることもありえるからです。
つまり、以下の二点のリスクやデメリットがあるため、そのような記載漏れとされうるケースでは、次の申請で以下のようにカバーが必要と考えます。
- 入管法第22条の4「在留資格の取消し処分」の事由における「不実の記載のある文書」提出であると、法務大臣(出入国在留管理庁長官)の裁量により評価される可能性がゼロではありません。
つまり、刑事処分だけでなく過料や行政処分が含まれる確率は低いがリスクは存在し、それが重大であるため、念のためにカバーする必要があります。
- さらに、理由書などで説明をすることで、次回の在留資格変更・在留期間更新の許可申請、あるいは永住許可申請を行う場合に、「素行善良」要件についての違反事実を不利に斟酌される可能性は十分にあるため、記載漏れであれば、過去に説明をしたことで、その事実は新たなものでなく払拭されたことをアピールできます。
2. 在留資格取消し(入管法22条の4)条文の構造
在留資格の取消しは入管法22条の4に規定され、①上陸拒否事由関係(1号)、②「偽りその他不正の手段」による許可(2号等)、③「不実記載のある文書等の提出」による許可(いわゆる“虚偽申請”に近い場面)(3号)などが並びます。(3)について入管庁は「偽りその他不正の手段は要件ではなく、申請人に故意は要しない」と明示しており、過失の提出であっても形式的には3号該当があり得る点に注意が必要です。実際の取消しは裁量行為であり、悪質性や重要性、弁明内容等を踏まえて判断されます。(法務省)
| 入管法 (在留資格の取消し) 第二十二条の四 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。 一 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。 二 前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。 三 前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。 |
3. 「上陸許可の証印等」には、更新・変更許可も含まれるか
3号は「不実記載のある文書の提出により上陸許可の証印等を受けたとき」を対象にします。この「上陸許可の証印等」には、本法の「この節(Residence)」による各許可が含まれ、在留期間の更新許可(21条)もここに入ると解されます(英訳条文でも “permission pursuant to the provisions of Chapter III, Section 1 or 2 (limited to those with a decision of status of residence)” と定義)。したがって、「更新申請での不実記載」も22条の4の射程に入ります。(日本法令外国語訳データベース)
| 在留資格の取消し(入管法第22条の4) 略 (3)(1)又は(2)に該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請人に故意があることは要しません。 |
出典:入管庁、https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/torikeshi_00002.html?utm_source=chatgpt.com
4. 申請書が問うのは「犯罪を理由とする処分」
更新申請書の当該欄は「犯罪を理由とする処分(※交通違反等による処分を含む)」の有無を尋ねています。ここで列挙されている「交通違反等」は、刑事罰(罰金・懲役等)に至った交通事案を含める趣旨で、単なる交通反則金の納付(青切符)や不起訴は、そのまま刑事処分とはなりません。ゆえに、罰金が科されていない限り、原則「無」で整合します(疑義防止のため任意の説明添付は推奨)。
5. 交通違反の3分類と法的帰結
(1) 反則金(青切符)で終了
交通反則通告制度は反則金を任意納付すれば公訴が提起されない制度です。刑事手続に移行しないため、刑事処分ではありません。よって原則「無」で整合します。
(2) 罰金(赤切符→略式命令)
罰金は刑事処分です。更新申請書は「有」とし、略式命令謄本や納付書の写し等で裏付けるのが原則です。過去の更新時に未申告がある場合は、3号の形式該当リスクがあるため、誠実な経緯説明と再発防止の提示が不可欠です。
(3) 不起訴(公訴提起なし)
検察官が起訴しないと決定したもので、裁判にも刑罰にも進みません。刑事処分は科されていないため、同欄は原則「無」。ただし、送致歴があるなど事実関係が複雑なときは、「◯年◯月◯日送致→◯◯地検で不起訴」と任意申出書で補足すると、照会・誤解を防げます。
6. 「偽りその他不正の手段(2号)」と「虚偽申請(3号)」の違い
- 偽りその他不正の手段(2号等):積極的な欺罔・重要事実の隠匿といった不正の“手段”が要件。典型的には故意が問題となり得ます。取消し条項だけでなく、刑罰法規(在留資格等不正取得罪)でも同一文言が用いられ、主観面の悪質性が焦点になりやすい領域です。
- 虚偽申請(3号相当):不実記載のある文書等の提出が核心。入管庁は「故意不要」と明示しており、過失提出でも形式該当し得ます。一方で、取消しは裁量であり、誤記の重要性・因果関係(その提出“により”許可を得たか)・弁明・是正状況が総合評価されます。
7. 不起訴ケースの取消しリスク評価
もし、結果、不起訴の場合は、刑事処分なしとなり、申請欄は「無」で整合し、虚偽申請(3号)に形式該当する余地は原則乏しい(虚偽の事実を記したわけではないため)こととなります。
過去の申請で「有無」欄を「無」としたこと自体が虚偽かは、「処分」の解釈と事実認識の相違が中心論点です。不起訴で処分なしであれば、「無」は合理的な記載で、取消しまで進むリスクは通常低いと評価できます。実務上の安全策として、任意の説明書で事実経過を明記し、入管からの資料追加の通知や問い合わせには即応できる資料(不起訴の連絡や記録等)を準備しておくとよいでしょう。
8. 実務ベストプラクティス(理論編の結語)
- 定義の厳密化:反則金≠罰金、不起訴=公訴提起なし。用語の混同を避ける。
- 様式の趣旨に忠実:問われているのは「犯罪を理由とする処分」。罰金があれば「有」、不起訴・反則金のみは原則「無」。
- 疑義は先取りで緩和:送致歴など判断が難しい場合は、任意の説明書でタイムラインを一行ずつ簡潔に示す(例:「YY/MM/DD 送致 → YY/MM/DD 不起訴。刑事処分なし。」)。
- 取消し条項の位置付け:3号は故意不要だが、取消しは裁量。重要性・因果関係・誠実な是正が評価される。不実記載がなく、単に“処分なし”を「無」としたにすぎない不起訴ケースは、取消しリスクは一般に低い。
参照情報(一次情報)
- 入管庁「在留資格の取消し(22条の4)」:3号は故意不要の明記あり。
- Japanese Law Translation:22条の4(Revocation of Status of Residence)の定義・本文。(日本法令外国語訳データベース)
- 警察庁資料:交通反則通告制度=納付で公訴提起なし(反則金は刑事処分ではない)。
- 裁判所・法務省(刑事)解説:不起訴=起訴しない処分の定義・趣旨。(裁判所)
※この「理論編」は、不起訴(罰金なし)までの範囲を対象に、条文と一次資料ベースで書かれています。実務上は個別事情で評価が大きく異なります。
続編の「提出資料(チェックリスト付き)編」では、説明書、添付資料の構成を詳述します。
⇒●「提出資料(チェックリスト付き)編」
CATEGORY
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。
- 対応サービス
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他