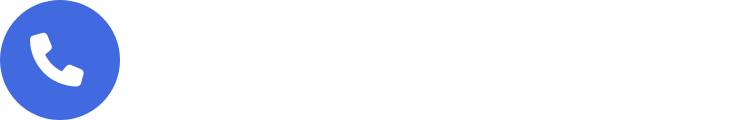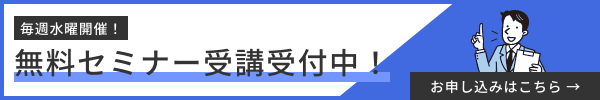【経営者・人事担当者必読】不法就労助長のリスク|「知らなかった」では済まされない刑罰と行政処分の違い
2025年08月02日
コンプライアンス在留資格一般
【経営者・人事担当者必読】不法就労助長のリスク|「知らなかった」では済まされない刑罰と行政処分の違い

外国人材の雇用がますます重要になる現代において、企業が直面するリスクの一つに「不法就労助長」があります。これは、不法就労とは知らずに外国人を雇用してしまった場合でも、事業主や担当者が重いペナルティを科される可能性がある、非常に深刻な問題です。
ペナルティには、「刑罰(不法就労助長罪)」と「行政処分(退去強制)」の2種類があり、それぞれ対象者や成立要件が異なります。特に、行政処分は過失がなくても成立し、外国人経営者や従業員が退去強制(国外追放)となるケースも含まれるため、最大限の注意が求められます。
本記事では、この2つの違いを明確にし、企業が取るべき具体的な対策について専門家の視点から解説します。
内容
【経営者・人事担当者必読】不法就労助長のリスク|「知らなかった」では済まされない刑罰と行政処分の違い
2. 【刑罰】不法就労助長罪とは?「過失」が認定されるケース
まず、「不法就労」とは、オーバーステイ以外にも資格外活動等も割と広く含めて入管法で定義されております。つまり、一般的な感覚で言われる、ビザなし外国人の不法就労以外にも広いです。例えば、不法残留などの不法滞在のほか、難民認定前の外国人が範囲外で働くことや、資格外活動許可なしの資格外活動も該当します。
さらに、企業の基準違反や、在留資格によっては「特定技能」や「技能実習」のように、許可後の企業の基準不適合まで資格外活動を構成し「不法就労」に含まれます。
不法就労を助長してしまった場合に科される可能性のある「刑罰」と「行政処分」の主な違いを比較表で確認しましょう。
| 刑罰(不法就労助長罪) | 行政処分(退去強制) | |
| 根拠法規 | 出入国管理及び難民認定法(入管法)第73条の2 | 入管法 第24条 |
| 対象者 | 事業者(法人、個人事業主)、斡旋者など(国籍を問わない) | 不法就労を助長した外国人(経営者、従業員、人材会社等の斡旋者、その他) |
| ペナルティの内容 | (改正法) 5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(または併科) | 本邦からの退去強制(さらに、一定期間、日本への上陸拒否も) |
| 成立要件(故意・過失) | 原則として故意が必要。 | 故意・過失を問わない(無過失責任) |
| ただし、不法就労と知らなかった点に「過失がない」ことを証明できなければ罰せられる(過失責任)。 | 結果として不法就労を助長した事実があれば成立する。 |
このように、刑罰は企業の代表者や採用担当者個人が対象となりうる一方、行政処分は関与した外国人自身が日本から追放されるという、全く異なる性質を持っています。次章からは、それぞれのリスクをより深く掘り下げて見ていきましょう。
2. 【刑罰】不法就労助長罪とは?「過失」が認定されるケース
不法就労助長罪は、事業活動に関して外国人に不法就労をさせたり、そのために外国人を自己の支配下に置いたり、斡旋したりした場合に成立します。
| 入管法 第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者 二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者 三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者 2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。 一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。 二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。 三 当該外国人が第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であること。 (以下略) |
この条文の重要なポイントは、第2項の但し書きにあります。
これは、「相手が不法就労者とは知らなかった」と主張するだけでは処罰を免れられないことを意味します。処罰を避けるには、「知らなかったことについて、一切の落ち度(過失)がなかった」ことを事業者側が証明しなくてはなりません。
◆「過失あり」と判断された実際の事例
毎日新聞の記事(2025年7月24日)の判例は、この「過失」の判断基準を具体的に示しています。
<判決のポイント> 新型コロナウイルス下を理由に、面接でベトナム人女性のマスクを外させて本人確認を怠った点について、裁判所は「マスクを外させていればなりすましを認識できた」とし、事業者の過失を認定しました。
この事例からわかるように、単に在留カードの提示を求めるだけでなく、顔写真と本人が同一人物であるかを確認するといった、基本的かつ確実な本人確認を怠った場合、「過失あり」と判断されるリスクが極めて高いのです。
刑罰とは別に、不法就労に関与した「外国人」が対象となるのが、退去強制という行政処分です。
| 入管法 (退去強制) 第二十四条 次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により本邦からの退去を強制し、又は第五十五条の二第一項の規定による命令により本邦から退去させることができる。 三の四 次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者 イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第十九条第一項若しくは第六十一条の二の七第一項の規定に違反する活動又は第七十条第一項第一号、第二号、第三号から第三号の三まで、第五号、第七号から第七号の三まで若しくは第八号の二から第八号の四までに掲げる者が行う活動(第四十四条の五第一項の規定による許可を受けて行う活動を除く。)であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。以下同じ。)をさせること。 ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。 ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。 |
ここでの最大のポイントは、刑罰と異なり「過失がなくても」処分が執行される点です。
執行されるというのは、行政不服審査法(本件は適用除外)や行政事件訴訟法等の執行停止を決定されない限り、執行されるという行政の原則通りです。
◆「過失がなくても退去強制は妥当」とされた高裁判決
これも毎日新聞の記事で報じられた東京高裁の判断が参考になります。
<高裁判決のポイント> 入管法の条文上、過失がなくても退去強制の理由となる不法就労助長は成立すると判断。
これは、出入国管理という国の行政秩序を維持するため、違反行為を行った者に対しては、その主観的な意図(わざとやったか、うっかりか)を問わずに厳格に適用されるという行政処分の性質を示しています。
つまり、外国人である経営者や人事担当者、現場の管理職が、たとえ細心の注意を払って採用活動を行ったとしても、結果的に偽造された在留カードなどを見抜けずに不法就労者を雇用してしまった場合、「不法就労を助けた」と判断され、退去強制の対象となりうるのです。これは企業にとって計り知れない損失に繋がります。
また、人材紹介会社なども「斡旋」行為によって、外国籍の担当者が退去強制の対象となるリスクを負っています。
これらの深刻なリスクを回避するため、企業は以下の対策を徹底する必要があります。
① 採用時の本人確認プロセスの厳格化
- 在留カードの原本確認: コピーではなく、必ず原本を提示させ、手に取って確認します。
- 顔写真との照合: マスクや帽子を外してもらい、顔写真と本人が同一人物であることを確実に確認します。
- 在留カードの真贋チェック:
- 偽造防止対策(ホログラムの動き、透かし文字など)を目視で確認します。
- 出入国在留管理庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」をスマートフォンに導入し、ICチップ情報を読み取ることを強く推奨します。
- 「在留カード等番号失効情報照会」ウェブサイトで、カード番号が有効かを確認します。
- 就労制限の有無の確認: 在留カード表面の「就労制限の有無」欄や、裏面の「資格外活動許可」欄を必ず確認し、許可された範囲での就労かを見極めます。
② 雇用後の管理体制の構築
- 在留期間の管理: 雇用している外国人の在留期間をデータで一元管理し、期限が近づいたら更新手続きを促す体制を整えます。
- 定期的な在留資格の確認: 在留資格の変更や更新があった場合は、その都度、新しい在留カードの提出を求め、内容を確認します。
③ 社内への周知・教育
採用担当者だけでなく、現場の管理職や経営層も含め、全社的に不法就労助長のリスクと正しい確認方法についての研修を定期的に実施することが重要です。
④ 谷島行政書士法人グループのシステム・仕組み化提案
在留資格の確認は、専門的な知識が必要です。ただし、基本的な確認は、仕組み化やシステムにより通常の人事業務を確実に行うこともできます。
谷島行政書士法人グループでは、専門的知識を提供する顧問契約から、基本的な確認手法のシステム構築+定例ミーティングでのWチェックの実行をクラウドシステムも使って提供しております。
不法就労助長のリスクは、「知らなかった」では決して済まされません。一つの見落としが、企業の信用失墜、代表者の刑事罰、そして大切な外国人従業員の退去強制という最悪の事態を招きかねません。
在留資格に関する法令は複雑で、改正も頻繁に行われます。自社での対応に少しでも不安を感じたら、自己判断で進めるのではなく、速やかに出入国管理業務の専門家である行政書士にご相談ください。
当法人では、各企業様の状況に応じた最適な採用プロセスの構築支援、在留資格に関するコンサルティング、そして日々の管理体制に関するアドバイスまで、ワンストップでサポートいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。
CATEGORY
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。
- 対応サービス
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他