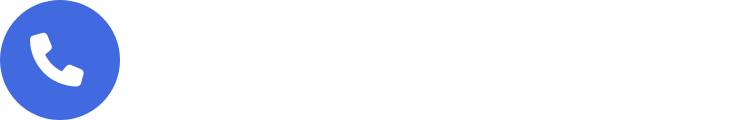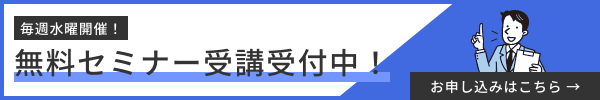在留更新・変更申請中の期限切れの時:「特例期間」計算を、民法総則「期間」で解決
2025年08月02日
在留資格一般
在留更新・変更申請中の期限切れの時:「特例期間」計算を、民法総則「期間」で解決

内容
民法第143条第2項(暦による期間)の応当日が2、4、6、9又は11月の末日ならどうなる?
午前零時から起算する(初日不算入とならない例外)の場合、満了日はどうなるのか
シナリオ1:日の途中から起算する場合(初日不算入が適用される)
特例期間とは
在留申請をする時、余裕がない状態でスタートすると、申請時には在留期限を経過してしまうことがあります。
これは申請受理がされていれば、その許可又は不許可の処分まで、又は在留期限の二カ月経過日までのいずれかが先に到来するまで、在留できるという規定です。
ただし、類型によっては、使えない場合もあるため、判断が必要です。
| 入管法 (在留資格の変更) 第二十条 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。 2 前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。 略 6 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。 |
入管法第20条第6項の規定における特例期間の満了日は、「従前の在留期間の満了の日から2ヶ月を経過する日」です。
それが最長と考え、入国審査官も許可又は不許可を出すことになります。
つまり、在留資格変更許可申請が在留期間満了日までに処分されない場合に、申請者が日本に引き続き在留できる期間を定めたものです。この特例は、申請に対する処分が下されるか、または従前の在留期間満了日から2ヶ月が経過する日の、いずれか早い方の時まで有効となります。
特例期間が使える場合と使えない場合
入管法20条6項のかっこ書きをみてわかるように、31日以上であることが要件です。
つまり、以下のように適合する例としない例があります。
| 在留資格 | 在留期間 | 結果 |
| 短期滞在 | 90日 | 可能 |
| 短期滞在 | 30日 | 不可能:オーバーステイ |
| 特定活動 | 6月 | 可能 |
| 特定活動 | 31日 | 可能 |
| 特定活動 | 30日 | 不可能:オーバーステイ |
短期滞在などであれば、親族訪問なら90日も出やすいでしょう。
これは告示外特定活動の変更許可申請を行う場合、必須の前提となります。告示外特定活動は、上陸基準省令及びそれに代わる告示がなく、在留資格認定証明書交付申請ができない類型だからです。
民法の期間の計算について補足
民法では、期間の計算について以下のように定められています。
- 初日不算入の原則: 期間を計算する際に、期間の起算日(この場合は従前の在留期間の満了の日)は含めません。
- 期間の末日で終了: 期間の末日が終了した時に期間は満了します。
例外は初日不算入の場合の前日満了です。
したがって、入管法の特例期間の満了日は、従前の在留期間の満了日の翌日から数えて2ヶ月目の日が終了する時となります。
民法の期間の計算に関する根拠規定は、主に以下の条文です。
| 民法 民法第138条(期間の計算の通則) 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。 民法第140条(期間の起算) 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 民法第141条(期間の満了) 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。 民法第143条(暦による期間の計算) 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 |
これらの条文が、日、週、月、年単位で定められた期間の計算方法の基本的なルールを定めています。特に、ご質問の入管法の特例期間のように「2ヶ月」といった月単位の期間については、民法第140条(初日不算入)と第143条(暦による期間計算)が重要な根拠となります。
在留期限の特例期間における初日不算入原則と満了日前日
例題:ある外国人の在留期限が2月1日で、1月25日に在留資格変更許可申請を行うと特例期間はいつまでか?
① 在留期間満了の日から二月が経過する日が終了する時 = 4月1日
② 当該処分がされた時 = 3月1日 までは適法に在留することができます。
また、結果が出ない場合のデッドラインは①です。
つまり、①か②のいずれか早い時までは適法に在留することができるというものです。もし、それまでに処分がなければ不法残留状態となりますが、上述の通り、入国審査官は在留期間満了後2月以内に処分を行うことが運用されております。
民法の原則の再確認:
- 民法第140条(初日不算入の原則): 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は算入しません。
- 民法第143条第2項(暦による期間の計算): 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了します。
上記の例(在留期限が2月1日の場合)の計算:
- 在留期限: 2月1日
- 特例期間の起算点: 「在留期間満了の日から二月を経過する日」という表現において、民法の「初日不算入の原則」を適用し、期間の計算は在留期限の翌日である2月2日から開始します。
- 2ヶ月後の応当日: 2月2日から2ヶ月後は4月2日です。
- 満了日: 民法第143条第2項の「起算日に応当する日の前日」という規定に従い、4月2日の前日である4月1日が特例期間の満了日となります。
したがって、「在留期間満了の日から二月が経過する日が終了する時 = 4月1日」は、民法の期間計算の原則を適用できます。
私の以前の例(7月1日が在留期限の場合)の訂正:
この原則を私の以前の例に当てはめると、以下のようになります。
- 在留期限: 7月1日
- 特例期間の起算点: 7月2日(初日不算入のため)
- 2ヶ月後の応当日: 9月2日
- 満了日: 民法第143条第2項の「起算日に応当する日の前日」に従い、応当日9月2日の前日である9月1日の終了時が特例期間の満了日となります。
以前の説明で「9月2日の終了時」としてしまった点は私の誤りでした。混乱を招き、申し訳ございません。
民法第143条第2項(暦による期間)の応当日が2、4、6、9又は11月の末日ならどうなる?
| 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 |
歴で計算する場合に翌月や翌年い「応当する日がないときは、その月の末日に満了する」という例外の意味は何でしょうか。
民法第143条第2項の理解を深めるために、以下のとおり、原則と例外の2つの例を三段論法に当てはめて説明します。
7月15日から2ヶ月間、という期間の満了日はいつか?
大前提(民法第143条第2項本文): 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
小前提(具体例への適用): この例では、期間は「7月15日から2ヶ月間」であり、月の初め(1日)から起算していません。
- 初日不算入の原則(民法第140条): 7月15日は期間に算入しないため、起算日は7月16日となる。
- 2ヶ月後の応当日: 起算日である7月16日から2ヶ月後の応当日は9月16日である。
結論(満了日): 大前提の「起算日に応当する日の前日に満了する」という規定に従い、9月16日の前日である9月15日の終了時が期間の満了日となる。
1月30日から1ヶ月間、という期間の満了日はいつか?
大前提(民法第143条第2項ただし書き): 月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
小前提(具体例への適用): この例では、期間は「1月30日から1ヶ月間」であり、月の初め(1日)から起算していません。
- 初日不算入の原則(民法第140条): 1月30日は期間に算入しないため、起算日は1月31日となる。
- 1ヶ月後の応当日: 起算日である1月31日から1ヶ月後の応当日は2月31日となるはずだが、2月には31日という日付が存在しない。
結論(満了日): 大前提の「最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する」というただし書きに従い、2月の末日である2月28日(閏年であれば2月29日)の終了時が期間の満了日となる。
午前零時から起算する(初日不算入とならない例外)の場合、満了日はどうなるのか
届出
初日不算入は応当日の前日に満了となるため、結論が変わります。
「初日不算入で応当日の前日に満了となる」のは、「月の初めから期間を起算しない場合」に適用される規定です。月の初めから起算する場合は、この「応当日の前日に満了」というルールは適用されません。
具体的な例で比較してみましょう。期間を「2ヶ月」と仮定します。
シナリオ1:日の途中から起算する場合(初日不算入が適用される)
- 例: 6月30日の途中から2ヶ月間
- 民法第140条(初日不算入): 6月30日は期間に算入しないため、期間の起算日は7月1日となる。
- 民法第143条第2項(本文): 月の初めから起算していないため、「起算日に応当する日の前日」に満了する。
- 起算日:7月1日
- 2ヶ月後の応当日:9月1日
- 満了日:応当日(9月1日)の前日である8月31日の終了時
- 例: 7月1日午前零時から2ヶ月間
- 民法第140条(ただし書き): 期間が月の初め(午前零時)から始まるため、初日は算入される(初日算入)。期間の起算日は7月1日となる。
- 民法第143条第1項: 期間は暦に従って計算し、民法第143条第2項本文の「応当日の前日」ルールは適用されない。
- 民法第141条(期間の満了): 末日の終了をもって満了する。
- 起算日:7月1日
- 2ヶ月後の応当日:9月1日
- 満了日:応当日(9月1日)の終了時
比較結果:
シナリオ1(6月30日の途中から2ヶ月):満了日は8月31日の終了時
- シナリオ2(7月1日午前零時から2ヶ月):満了日は9月1日の終了時
このように、日の途中から起算するか、午前零時から起算するかによって、満了日は1日異なることになります。
つまり、午前零時までは前日からの起算の初日不算入をするときと同じ満了日になりますね。
特例期間の場合、二カ月が起算されるのは、「在留期間の満了の日から二月」という在留期限日からになります。この点、満了日である日の午前零時から起算されるとなると、初日不算入とならず、二カ月経過が早まります。
しかし、特定技能所属機関による入管法の届出等では、14日以内という、日によって定めていることで初日不算入される原則通りではないかと考えます。
| 民法 (期間の起算) 第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 |
所属機関に関する届出等(技術・人文知識・国際業務等)の場合
この点、転職などの所属機関に関する届出では異なります。
つまり起算日は事由発生である日の途中であるため、初日不算入をして、14日という歴計算で、初日不算入となるため、15日目が応当日である満了日と考えられます
特定技能、その他の在留資格の所属機関に関する届出等の場合
特定技能所属機関による届出も同様です。
| (特定技能所属機関による届出) 第十九条の十七 法第十九条の十八第一項に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号並びに別表第三の五の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。 2 法第十九条の十八第一項の届出をしようとする特定技能所属機関は、同項各号に定める事由が生じた日から十四日以内に、同項各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を、地方出入国在留管理局に提出しなければならない。 |
起算日が日の途中からの場合、初日不算入となります。
例えば、1月15日に労働契約等の変更が特定技能所属機関による随時届出の事由とします。
この点、上記入管法19条の17二項は、事由発生日であるから日の途中です(「事由が生じた日から十四日以内に」)。
したがって、初日不算入であって、1月16日が起算日となり、143条の前日満了となる例外が適用される週、月、年ではないため、応当日が満了日です。
結論、この例では30日が応当日で満了日となります。
特例期間中の就労と再入国許可の可否
特例期間中は、在留できるとなっておりますが、就労活動等も同様に行うことが可能です。
ただし技能実習からの変更を除きます。これは「技能実習計画中」であることが活動となる要件であるからです。そのような類型の計画関係以外、ほとんどは就労可能です。
さらには、再入国までも可能となっております。
ただし、再入国は、失効または上陸拒否リスクがあると伝えることにはなります。これは後発的事情も関係し、とりわけみなし許可の場合、より気を付けることになります。
CATEGORY
この記事の監修者

-
谷島行政書士法人グループCEO・特定行政書士
外国人雇用・ビザの専門家として手続代理と顧問アドバイザリーを提供。ビザ・許認可など法規制クリアの実績は延1万件以上。
- 講師実績
▶ ご依頼、セミナー、取材等のお問合せはこちら
行政書士会、建設やホテル人材等の企業、在留資格研究会等の団体、大手士業事務所、その他外国人の講義なら幅広く依頼を受ける。
- 対応サービス
- 資格等
特定行政書士、宅建士、アメリカMBA・TOEIC、中国語(HSK2級)他
- 略歴等
・札幌生まれ、仙台育ち、18歳から東京の大学へ進学。
・自身が10代から15種ほどの職種を経験したことから、事業のコンサルと経営に興味を持ち、その近道と考え行政書士受験、独学合格(合格率2.6%)。
・行政書士・司法書士合同事務所を経験後、大和ハウス工業㈱に入社。「泥くさい地域密着営業」を経験。
・独立し業務歴15年以上、マサチューセッツ州立大学MBA課程修了、現在に至る。
- 取引先、業務対応実績一部
・企業:外国上場企業などグローバル企業、建設など現場系の外国人雇用企業
・外国人個人:漫画家、芸能人(アイドルグループ、ハリウッドセレブ)、一般企業勤務者他